 �@�������͂��Ȃ��ŁA���̂ق��͂�����蕲�Ŋۂ߂�
�@�������͂��Ȃ��ŁA���̂ق��͂�����蕲�Ŋۂ߂�2005�N12���̕�炵
12��31��(�y)�����@�@2005�N�́[�ƁE�炢�ӑ���10��j���[�X
��1�ʁ@NHK���[���h�J�����_�[����(�|���|��)
��2�ʁ@�l���\�E���g��100�L���}���\�������A12����53��(�|���|��)
��3�ʁ@�l���\��45�L���J�i�f�B�A���ʼn���A8����
��4�ʁ@���l�L�X�ނ���D���A�務�ܓƐ�(�|���|��)
��5�ʁ@�u��12��`�����e�B�[��̎�d���W�v�J��
��6�ʁ@����V�z�A�K���[�W�V���b�v�I�[�v��
��7�ʁ@������}���\�����3�ʓ���(�|���|��)
��8�ʁ@���W�A�s�W�A�e��ʐ^�R���e�X�g�œ���(�|���|��)
��9�ʁ@�l���\��45���ԂɃX�Y�L4�C�ނ�(�|���|��)
��10�ʁ@�{�����e�B�A����������(�|���|���E�L���R)
���_�@�܂����⍜��(�L���R)�E�E�E�����������ЊQ��B
2005�N��U��Ԃ��Ă݂�A���낢��Ȃ��Ƃ�����܂����B
�Љ�͂܂��܂������ɂ����Ȃ�A���̂�ЊQ����������܂����B
����Ȓ��ŁA���C�ɕ�点�������ł��K���Ȃ̂����m��܂���B
�����o���y�������Ƃ������ς����������A�t�ɐM�����Ȃ��悤�ȏo�����ɂ��������܂������A���ꂪ�l���ł��ˁB
���낢��Ȑl�����邩��A�����l�Ƃ̏o��Ɋ��ӂ������Ȃ�̂��Ǝv���܂��B
�l���͒Z���B���͂ł��邾���A����������́A���������́A�D���Ȃ��́A�ɐS�ʂ킹�Đ��������Ǝv���Ă��܂��B�K���A���̎���ɂ͂����ς�����܂��B
�����āA�������������w�͂�ɂ��݂܂���B���N�����������܂��B
2006�N�����a�ŁA�݂Ȃ��܂ɂƂ��čK�������ς��̂悢�N�ł���܂��悤�ɁE�E�E�B
12��30��(��)����@��������
29���͑�|���A30���͂��������A31���͂������l�̏����B���U�͂��Ƃ�̍s�������āA���G�ς�H�ׂāA�O�Ђ̎��_�l�ɏ��w�A���̂��Ƃ���Q��B
���N�A���N�A���ʼn������悤�ȉ䂪�Ƃ̔N���N�n���B���S���Ă���A�܂������ς���Ă��Ȃ��B
���N�͂�����ƈ���āA29���͑�|���ł͂Ȃ����|�����ߑO�����������Ƃ��āA�吨�̂��q�l�łɂ�������B�Ƃ��Ă��y��������������B
�悫�l�����Ƃ̌�炢�قǁA���C�����炦����̂͂Ȃ��B�Ō�̂��q�l���������Ă���A������������Ă�Z����̂�Y��ĐQ�Ă��܂����B
���������͑O�邩�珀�������Ă����̂��B���s�B
����Ԃł����Ă𐅂ɐZ���A���̊Ԃɂ������A����W�����ăE�b�h�f�b�L�Ɋ����Ă����B�ߌ�1�����炨���������X�^�[�g�B
�܂��͋��������B���ꂩ��A���d�˂�����12�g�B��������~���āA2�i�d�˂̂�������_�I���_�{�l�①��H�[�◣��E�E�E�A���낢��ȏꏊ�ɍՂ��Ă����B�͔̂_��ɂ��Ղ��Ă����B�u���̈�N����J�l�v�̈Ӗ����낤�B
���̂��Ƃ͂�����6��ނ̂��������ۂ߂��B�������ƌÑ�Ă����ƈ��������A������ꂽ�̂Ɠ���Ȃ��̂����B
�q�ǂ��̍����炨�������͎�`���Ă����̂ŁA���ꂽ���̂��B�͉̂��������肩�̑�d�����������ǁA���͓���������`���Ă��炦�Α��v�B���Č������A���̎q�ǂ������ɂ����̓`����`�������Ǝv���B
����������ł������Ă��邨�����B�ł��A�����ŏ������āA��̔��^���Ԃɂ��ĔM�X���ۂ߂āA�傫���̂�珬�����̂�炢�тȂ̂�炢�낢�날�邯��ǁA�ق����ɕ������Ȃ�������Ă̂�������j�����āA�u���������ˁ[�v�ƌ����Ȃ�����{�������ށB
�r���ł��Ε��͂��ɗ��Ă��ꂽ�l�������肷��ƁA�u�܂��オ���Ă����āB�������ł��H�ׂāv�Ȃ�Č����̂��A�N�̐��ɂӂ��킵���K���ɂȂ�B
 �@�������͂��Ȃ��ŁA���̂ق��͂�����蕲�Ŋۂ߂�
�@�������͂��Ȃ��ŁA���̂ق��͂�����蕲�Ŋۂ߂�
�P�Q��25���i���j�����@�����ψ�
���N����2���ƁA�N�̕��̂Q��A�n��̐l�X���S���o�Ȃ̉������B
�n��ł̂��낢��Ȍ��܂育�Ƃ�s��������̂ŁA��v��������A���N�x�̈ψ�����3����I���Ō��߂�̂��B
�|���|�����A���Ă���Ȃ�A�u���N�̈ψ��ɂȂ����v�ƌ����̂ŁA�Ђ��[�[�Ǝv�킸�������B
�u�����Ăh�^�[���̂��Ȃ�����Ȃ��Ă��A���̓y�n�ɐ��܂������N��̐l�����������ς�����ł��傤�H�I�v�ƌ����ƁA�u�l�����Ă����v�����v�B
�ǂ����ĕ[���W�܂����̂��낤�B���̐����ł́A���R�Ԓ��ڎx�������x�̉��5�N�Ԃ�������Ƃ��v�����Ǝv���B
���N�ł��̖����I���B���͈ψ��ɁE�E�E�ƍl�����l�������̂��낤�B
���N��N�Ԃ͈ψ���ɏo�Ȃ��A�n��̂��낢��Ȗ��ɂ��Ęb����������A������ɒ�ɍs������A�V�����̌����������Ƃ��낤�B
�ł��A�l���Ă݂�A�h�^�[�������炱���̐V�N�Ȏ��_�ŁA�n��̂��Ƃ��l����ψ����P�l���炢�����Ă��Ă��������낢��Ȃ��́B
�|���|���͒n��̂��Ƃ͈�Ԍo���s�����Ǝv�����A���܂��܂ȍ��ŕ�炵�Ă����Ƃ����_�ł́A�|���|������Ԃ��Ǝv������B
12��24���i�y�j����@����
���͋C�y�搶��ŃC���~�l�[�V�����߂Ȃ���A�y�����W���i�����B
���O����̏��Ζʂ̕��������̂����A�����b�������Ɂu���������N�ł���l��������v�Ɠ`����Ă���B
�����A�l�Ԃ͎��ȂB�����u���������҂́A���͂ň����ꍇ������A�o��ׂ����ďo��̂��낤�B���͈͂ӎu���B
�������Đl�͂Ȃ����Ă����B�Ȃ��邱�Ƃ͂ƂĂ���Ȃ��Ƃ��B
�C���̍����͂��V�C���悭�A���������낢�����Ă݂�ȂŎ��H�����B
�H�ׂ�Ƃ������Ƃ́A�����邱�Ƃ��B�ґ�ȗ����ł͂Ȃ��Ă��A��������Ĉ�Ă����̂��ł��邾�����������H�ׂ����B
��̃T�j�[���^�X���g�����芪�����i�A�Ƃ��Ă��������������B
���N�̃N���X�}�X�P�[�L��䕖��B�`�L���̓X�p�C�V�[�ƏƂ�Ă��ƂQ��ޏĂ��āA�ׂ̂����ɂ��͂������ꂽ�B
 �@�C�y�搶��̃C���~�l�[�V����
�@�C�y�搶��̃C���~�l�[�V����
12��22���i�j����@��
���N������A��������B�����͉����Ⴊ�~�������A����������Ȃ��Ȃ�قǂ��B
��������ԐϐႪ�����āA�x�����_��15�Z���`�������B
�|���|�����Ⴉ�������Ă��ꂽ���A���ɓ����Ă��ĕ����̂������B
��������������Ⴂ�āA�o�X�����炸�A�X�։���������Ȃ��B�f�B�T�[�r�X�����̍s�����A�݂�Ȓ��~�ɂȂ����B
�����������m�g�[���̐Î�̐��E�B���l�̑��̂悤�ɂȂ��Ă��܂��āA�Ȃ������������ɉ�����ɂ��Ȃ��B
�ፑ�̐l�����́A����Ȃ̂����������̂��낤���B�ۑ��H�̕K�v����������B
��Ԃ̂̓��N�ƃn�i����B�{�����̐��������āA�Y�{�V���[�͓{��̋������������B
�����͐���܂��悤�ɁB
 �@����Ƃ������瑾�z���������u�ԁA�ł������E�E�E
�@����Ƃ������瑾�z���������u�ԁA�ł������E�E�E
12��17��(�y)��@�`�����e�B�[�W�I���
���N�̃`�����e�B�[��d���W���I���B
�Ⴊ�����ĐS�z���������A��N��300���ȏ�̕������Ă��������āA���������ς��̎�d���W�������B
�X�^�b�t�͂��ߊ��Ԓ������łĂ����������݂Ȃ���A�������グ�������������X�A��i����Ă����������݂Ȃ���AHP�ʼn������Ă����������݂Ȃ���A�}�X�R�~�e�Ђ݂̂Ȃ���A�ق�Ƃɂ��肪�Ƃ��������܂��B
�ߎS�ȃj���[�X���肫��Ȃ������������ς��̐��̒��A�M�����Ȃ��Љ�B
�ł��A���̂R���Ԃ͐l�̗D������P�ӂ������ς��A����Ȏ��Ԃ����L�ł��Ăق�Ƃ��ɍK�����Ǝv�����B
��Ւ���̐{��搶�̂��ꂳ�܂�88�B�u���̍�i�W�������āA���������ėǂ������B���N�͎����o�������v�Ƃ���������Ă����������B
���Ђ���!�@���ꂪ�u��̎�d���W�v�́u�炵���v�����́B
���N��10�ォ��60�ゾ�������ǁA���N��80��ɂȂ邩���m��Ȃ��Ȃ�āA���ꂵ���b���B
���Q����10��̈ɑタ��ƂĂ��������肵�Ă��āA���̂R���ԂŊ��S�����肾�����B
��i�̑O�œށX�����Ɠ�l���ʐ^�́A���炵���Ί�! ���߂Ă���҂����ꂵ���Ȃ�悤�ȏΊ炪�A�Ȃɂ����u�y���������v�Ƃ������t����Ă���B
�ɑタ���̂��ꂳ��ɂ́A��������Еt���܂Ŗ{���ɂ����b�ɂȂ���ςȂ��������B
���N���E�삩��삯���Ă����������A���c�����̂��ꂳ��B
���C����͓������痈���F�B���ē����Ă�������A��ԉ�������̂��q���܂ɂȂ����B
�C���̃~�c����Ƃ�\����̂���l�B�������ԑт�������A���Ђ��Љ�����������ǁB
�����q��A������W���̑�H�����T������A�q�ǂ������A��ė��Ă����������B�݂�Ȃ݂�Ȃ����ւ�Ȏv��������āA������Ă���l�����B�Ȃ�ėD�����A���肰�Ȃ��̂��낤�B
�����Ƃ����ւ��炱���A�D�����̂��B�l�̒ɂ݂�������̂��B
���N����l�Ƒ��q����ƎO�l�ŗ��Ă��������Ă���O����́A���N�͑��q����Ɠ�l�������B����l����삷�閈�����ƁA�b���ċA��ꂽ�B
���M�Ƃ̂���l�́A��d���W�̂��Ƃ��G���ɏ����Ď����ė��Ă������������Ƃ��������̂ɁB
�V���o�[�J�[�������āA����낵�Ȃ��疈�N�����������Ă�������n�c�R����B
���N�͍ŏI���ɂȂ��Ă��p���������A�u��Ŋ�������o���Ȃ��̂�����B����Ƃ��A�܂����Q������ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����낤�Ȃ��v�ƐS�z���Ă�����A�Еt���鎞�Ԃ��肬��ɂȂ��ď�����ď����ȑ̂œ����ė����B
�m���A���N�������������̂��B80���Ƃ����ɉ߂����l���A���N�V�����X�g�[���ƐV�����֎q��K�v�Ƃ��Ă���Ƃ͎v���Ȃ��B���������������̊����������������ŁA���Ă�������̂��낤�B
����ȑP�ӂ̐l�X�ƁA�N�Ɉ�x�̏o��B���Œm�荇���āA�܂����N���y���݂ɂ��ʂꂷ��B
���̊����ɗ͂āA���N�͂�����V���ȃX�e�b�v�ݏo�����Ǝv���Ă���B
 �@���q���܂łɂ��키���
�@���q���܂łɂ��키���
12��14��(��)��̂�����@�u�c�ɕ�炵�̖{�v
�����̕Ђ�S�ҏW������ƁA�J�����}������ނɗ���ꂽ�B
�����u�c�ɕ�炵�̖{�v�́A�����|���|�����ȑO���ǂ��Ă����G���ŁA�{�I�ɂ���̂�������Â����̂�1992�N����A�V��������1997�N�̔��s�������B
����l�Ƃ��ƂĂ������̂������ŁA��ނ�Y��Ęb������ł������y���������B
�ق�Ƃɔ����A�����ēI�m�ɔ������Ă�������̂ŁA�����ւ���ɂȂ�B
�|���|���̓J�����}������ɋ�������ŁA�J������B�e�̎d����M�S�Ɋώ@���Ă��镗�������B�@
���N��n�i�܂ōڂ��Ă������邱�ƂɂȂ��āA�Z��Ɏ̂Ă��Ă�����C�����悢��S���f�r���[�B���h�������B
 �@�c�ɕ�炵�̖{�P����
�@�c�ɕ�炵�̖{�P����
12��13��(��)��@����搶
����Ȃ��Ƃ��Ă����ł��ˁ[�B
����搶���Ɛ��J�C�搶�̍u��������āA�|���|���ƓށX�����Əo�����܂����B
�u����Ȃ��q�ǂ������v�Ƃ�������ŁA���ׂĂ̑�l�����ɕ����Ăق������e�̘b�ł����B
��̒��A�������Ȃ�̂��́A�����ŏ[������ĊO�ɏo���̂ł��B
���r�[�œށX�����́A�u���肵�Ă��炢�����Ȃ��v�ƃL�����L�������Ă����̂ł����A�u������B�����ĖZ�������炷���ɏ��R�ֈړ����ƌ����Ă��ł���v�ƌ����āA���ԏ�ɏo���̂ł��B
�Ⴊ���������Ă��܂����B
�Ԃ̂Ƃ���ŁA�ӂƌ����̗����������A�X�[�c�p�̒j�����^�o�R���z���Ă����̂ł��B
���C�Ȃ�������A������ƏƂꂽ�悤�Ɍy����߂��܂����B���ꂢ�ȓ��B�u?!!�B�܂������v
�u�ԁA�u�ށX�����A����!�v�Ɣ�яオ���Ă��܂��܂����B
���J�搶�������̂ł��B�߂Â��āu���肵�Ă���Ă��������v�ƌ����ƁA�����Ƀ^�o�R��������(�������v���ΐ\����Ȃ����Ƃ��E�E�E)�A�ށX�����ƈ��肵�Ă���܂����B
�ʐ^������ŎB���Ă��������āA�ق�ƂɗD�����X�e�L�Ȑ搶�ł����B
����ɂ��Ă��A����͓ށX�����ւ̐_�l�̃v���[���g�ł��ˁB
���N�A�ށX�����́A�h�тł̓����L�[�搶�ƈ��肵�A����͂��Ԃ�����l��������搶�Ƃ��ʐ^���B���Ă��炢�A�V�ɂ��̂ڂ肻���ɋ������Ă��܂����B
12��11��(�y)����@��Ւ���Ǝh���q
�����Ƃ��̂��炠����{�̓`�������ŁA�����C�N�Ƃ����_�����ʂ���B
��Ւ���͔_�Պ��ɁA���|�����Ȃǂɘa����\���āA�`�a��h���čĐ����Ďg�����̂��n�܂肾�B
�|�������a�����̂���`�a���E�E�E�A�����ƑS�����肾�����̂��낤�B
�g���Ȃ��Ȃ������̂��A�Ȃ���ɂ�݂����点�Ĉ��p���悤�Ƃ���S���D���B�������Ւ�����D���Ȃ̂����m��Ȃ��B
�h���q���������B�C�y�搶�ɂ��肵���h���q�̔��Z�́A���z�Ɉ�j��j�h���ď�v�ɂ��Ē��Ă����B
�ׂ��Ȑj�ڂ��т�����Ǝh���̂́A��Ȃd���������̂����m��Ȃ��B
���Ԃ͖�ǂœ����A��͈͘F���̂��ł������Ǝ�d��������B�G�̂悤�Ɍ��i��������ł���B
�����C�N�Ƃ����A���̓�����ł͂Ȃ��B�Õz�߂����������A��܂̃o�b�N�������B�؍H�����āA�̂Ă����[�ނ��Ɏ��グ�č�i�ɂ��Ă���B
���̐��߂��A��������߂���A���Z�[�^�[���قǂ��Đ��߂���A�������������C�N���Ă���B
�u��̎�d���W�v�́A�����Ȍ|�p��i�W�ł͂Ȃ��B
�����Ɩ��ڂɌ��т��āA���̂Ă�ꂻ���Ȃ��̂J�Ɉ����č�i�ɂ���E�E�E����ȂƂ��낪�A�����ւ�Ɏv���_���B
���ЁA�����̐l�Ɍ��ɗ��Ăق����B
 �@�H�c�h���q�̑��Ȃ����Z(������ł͂������ƌĂ�)
�@�H�c�h���q�̑��Ȃ����Z(������ł͂������ƌĂ�)
12��5��(��)��@���̒��ɂ͂������l�������ς�����
�܂����̐�B��N��葁���悤�ȋC�����邪�A�P�Q��������s�v�c�ł��Ȃ����B
���A�e���r�łƂĂ������I�ȃh�L�������^���[�ԑg������Ă����B
���E�I�ȉȊw�҂̐搶���]�[�ǂœ|��A���n�r�������Ȃ���PC�ňӎv��`���A�Ȃ�Ɩ{���o�ł��Ă���̂�!
�ꌩ����ƁA��ʂ̔]�[�ǂ̐l�ƂȂ��ς��Ȃ��B���g�}�q���A�悾�ꂪ����A���t���o�Ȃ��B����v���o�����B
�ł��A�搶���u�a�ɓ|��Ď��������̂��傫�����A�V���ɐ��܂����̂�����v�ƌ����̂��B
�����āA�u���̂ق������ǂ������Ă��邩������Ȃ��v�ƁB
�������A�����ɂ���ȐS���ɂȂ����̂ł͂Ȃ��A���x�������l�����������B
���l�����Ȉゾ���A�b�܂ꂽ���ɂ������Ƃ͂����A��ʂ��猩��搶�̎p�Ɉ��|���ꂽ�B
�l�Ԃ͒�m��Ȃ��͂������Ă���B����͗\���ł��Ȃ����炢�傫�ȗ͂��B
�搶�����ďW�܂��q�����̉�ɏo�Ȃ��A�K���ŌP�����Ĕ������u�J�E���E�p�E�C!�v
�ӎނ����������A�q�ǂ��̂悤�ȏΊ�Ŋy���ށB���ɂ��C��z��B
���̂ق������ǂ������Ă���A���̌��t��������ł͂Ȃ����Ƃ��A�������搶���g���ؖ����Ă����B�����A���̒��ɂ͂܂��܂������ς��������l������B
�q�ϓI�ɗ^����ꂽ���̂��A�K�s�K�f����̂ł͂Ȃ��B�����ɐ����邩���B
 �@�|���|���H�[��Ԃ̏�蕨�A�ؔn�Ƃ������ᔠ�ƎO�֎�
�@�|���|���H�[��Ԃ̏�蕨�A�ؔn�Ƃ������ᔠ�ƎO�֎�
12��4��(��)�J�@�ق��ƃu�V����
�₽���J��������~�������j���B���悢��{�i�I�ȓ~�������B
�d�X�g�[�u������������āA�����̒����ۂ��ۂ��ɒg�߁A�u�ق��ƃu�V�����v�����ށB
������Ƌ����������ȁB�ق��ƃ������Ƃ��A�ق��ƃI�����W�̕���������ꂾ�B
�ł��A���������ł͕����Ȃ��B
����ɂȂ��Ă���u�V�������A���F���F�Â��ď����Î_���ς��Ȃ����B
��ɐ��āA������1�J�b�v�ɍi��B����Ƀn�`�~�c�������A�M���ł̂��������̈��ݕ������A���ꂪ���������̂�ˁ[�B
���ׂ̈����n�߂��炢��������A�ꔭ�Ŏ���B�܂邲�ƃr�^�~��C���Ċ����B
�������A�������u���������A���������v�ƈ���ł���̂́A�W���X�~���e�B�[���B
�����v�[�P�b�g���炨�y�Y�ɔ����Ă��Ă��ꂽ���̂ŁA�p�b�P�[�W���ƂĂ������B
���߂Ă��ꂵ���Ȃ�A����ōK���ɂȂ�B�e�B�[�^�C���́A�����̖����B
�H����1�H��2�H�����Ă����C�����A���ݕ������͌������Ȃ��B
2005�N11���̕�炵
11���Q�R��(��)����@���p��
�f���ł̂�����Ă���Ă����u�ʐ^�v�́A���p���̒��x���i�̂��Ƃ��B
�������x�݂ɂȂ�ƁA�P�N���Q�N���R�N���A�w�N���Ƃ킸�吨�̐��k���������p���ɂ���Ă���B
�L���R�搶�͑�Z�����B���܂��Ă��w�Z�����͋x�݂����Ȃ������̂́A���͎��Ƃƕ��Ԃ��炢���x�݂̐��k�Ƃ̂ӂꂠ�����傫�������B
�ŏ���3�K�̋������n�܂肾�����B
���x�݂ɂȂ�Ƒ吨�̐��k������悤�ɂȂ�A�u�����ɗ���Ƃق��Ƃ���v�Ə�A�����S����Ԃ₢�āu�ق��ƃX�y�[�X�v�Ɩ��Â����B
�ł��A���̋��S�n�̂��������͂܂��Ȃ��u�g�p�֎~�v�������āA�g���Ȃ��Ȃ����B
�s�o�Z�̐��k�̂��߂̕����Ȃ̂�����Ƃ������Ƃ������B���ۂ͑S���g���Ă��Ȃ��̂ŁA�����s�o�Z�̐��k���o�Z���Ă��Ă��A�ق��̐��k���o����ł���̂������Ȃ��Ǝv�������A���ǃ_���������B
���낢�둊�k�ɗ��Ă������k�����������̂ŁA2�K�́u���k���v���g�����Ƃɂ����B�����͖ؗj���̔��������X�N�[���J�E���Z���[���g���Ă��邪�A���Ƃ͋Ă���B
�܂����k���u���k���v�ɏW�܂肾�������A�������u�g�p�֎~�v�ɂȂ����B���x�͒��x�݂ɐ��k������Ƃ���֓����Ă��ċ֎~������ꂽ�̂ŁA�������q�������̂��h�������B
���ǁA�w�Z�ň�ԉ����u���p���v�ɗ��������āA�܂��吨�̐��k�������W�܂��Ă��Ă���B
���܂ł̓�̕����Ƃ͔�ׂ��̂ɂȂ�Ȃ��قNJ��͂悭�Ȃ����A����ł����k�͂����Ƃ��ς�炸�W�܂��Ă��邱�Ƃ��v���ƁA�|���|�����u�������p�����_���ɂȂ�����x�����_�ł��ǂ��ł��A���Ȃ��̍s���Ƃ���ɐ��k�͏W�܂��v�ƌ����ʂ肩���m��Ȃ��Ǝv���n�߂��B
���́A�����Y�݂������ƃL���R�搶��K�˂Ă͂����Ȃ��A�ƃJ���Ⴂ���Ă��鐶�k�����邱�ƁB
W�N���^���Ȋ�ŁA�u�ڂ��L���R�搶�ɑ��k���������ǁA�Ȃ���Y�݂��Ȃ�����E�E�E�B���[�A�������A�P���ʂ����܂��Ȃ���@�K���ɍs���Ă�����?!�v�ɂ͏����B
���x�݂����ł͂Ȃ��B�x�ݎ��Ԃ����ی���A���k�����͐E�����Ɂu�L���R�搶�v�Ǝ菵���ɗ���B
��肩���Ă���d���������Ă��K�������āA�L���̒��֎q�Řb������B������x�����B
�ׂɎ��͑傫�ȗ͂ȂǂȂ��B�ł��A�q�ǂ��̋��߂ɂł��邾���͂ɂȂ肽���Ǝv���̂́A��l�Ȃ瓖�R�̂��Ƃ��B
�����Ă���́A�����g���q�ǂ�������炤�u�����v���A�͂邩�ɑ傫�����Ƃ�m���Ă���B
����A�h�N�^�[�X�g�b�v���������Ă���A�����×{�����Ă�����Ă��āA���p���ɍs���Ȃ��Ȃ��Ă���B
���l������u�搶�ǂ����ĊJ���������B�l������s�����ɁE�E�E�v�ƌ���ꂽ�B
���߂�A���߂�B�������������Ă��������܂��J���邩��A�҂��ĂĂˁB
11��18��(��)����@Rural Stage (Gold Prize)by Hirosi Chiba
NHK����d�b�������āA����7��55������|���|���̎ʐ^���Љ���Ƃ������Ƃ������B
�u�e���}�b�v�v�Ƃ����ԑg�ŁA���N�x�̃��[���h�J�����_�[�̏Љ�ƁA���T�����R�����Ă���Ƃ���A�����ċ��܂̃|���|���̍�i�̃R�����g�����Ă����������B
�����S�\�a���̒I�c�ő���������Ă��镗�i�ƁA���m���@��t�@�m�@����ƃe���b�v���o���B
���傤�ǓށX������Ă��āA��l�Łu��[�A��[�v�����Ō������A�{�l�͂����̒ʂ��Â������B
�J�����_�[�̌��{���͂��āA8���̂Ƃ���Ɏʐ^�ƃ^�C�g���A���܁@�����@�B�e�n�A���{��Ɖp��̐��������Ă����B
���[���h�J�����_�[�Ȃ̂ŁA�O���ɂ����N�����Ă���킯���B�p��̐����͂���Ȃӂ��������B
There are numerous terraced rice-paddies in the village of Toowa and elsewhere along
the middle reaches of the Shimanto River in Kochi prefecture, Shikoku. A farmers wife
is trimming the grass on a terrace separating two fields of rice. The terraced paddies,
illuminated by the afternoon sun, appear as a stage.
���̓|���|������܂��邫������������Ă��ꂽ�̂́A�\���N���O���疈�N�N���ɃJ�����_�[�𑗂��Ă��Ă��������Ă���K�f�B���N�^�[���B
NHK�̖��É��ǂŁu���w�����L�v�̃`�[�t�f�B���N�^�[������Ă������ɁA�킴�킴�n�ׂ܂Ń��P�ɗ��Ă����������̂��o��������B���̎��́u���搶�v�����w�����L�̐搶�������B
���ꂩ��a�J��NHK�ɓ]�ɂȂ��Ă��A�����Ɖ䂪�Ƃɂ�NHK�̃J�����_�[�������A�������S����ɕۊǂ��Ă���B
���É���NHK�ɂ��a�J�ɂ��AK�f�B���N�^�[�����K�˂����Ƃ�����B�����āAK���g���ʐ^����D���ŁA�ސE������J�����������œ��{���𗷂���̂����ŁA�u����l�̓��C�o���ł��v�Ə��Ă����̂��B
�{���Ȃ��܂������������ɁA�^����ɂ���������ׂ��l�Ȃ̂����A���͂܂��ق��Ă���B
K���u�J�����_�[�������Ĉ�x�ɑS�������A�����߂��������Ɏʐ^�Əo��̂��y���݂ɂ��Ă����ł��v�Ƃ���������Ă����̂��o���Ă��邩�炾�B
8���Ƀ|���|���̎ʐ^�����āA�u�������[!�v�Ƌ�������̂��y�������ȂƎv���āB
11��17��(��)����@�H�̕ւ�
��a�������Ȃ���A�����������d���W�Ɋ���o���Ă�������M����A�t�����͂����B
����{�ɂ������悤�Ȃ��ꂢ�ȕ����ŁA�ׂ����т�����B
���[���Ɋ���Ă������̍��A����ȗt�������Ƃ��݂��݂Ƃ��̐l�������̂��C������B
�s�@�O���@���l���y���ނ��̂悤�Ɋ`�̎����n��A�H���[�܂��ĎQ��܂����B���ς��Ȃ����߂����ł����B
�@�y�j���A�p�b�`���[�N�W�ɍs���A����ł��ٓ����A�n�ׂւƎf���܂����B�r���A�H�������������̓c��ڂɔ������炫�A����ڂ��y���܂��Ă���܂����B
�@���L�̓�������H�����炢�Ă���Ƃ���ŎԂ��~�߁A����ɉ���čs���A�P�l�ł��ٓ���H�ׂ܂����B��j�i������A���̗�������āA���R���Ă����Ȃ��[�B��C�����������A�ꐡ���肨�Z���`�C���ɂЂ����Ă��܂����B
�@���q�œ����̕ەꂳ����A���T�u���[�𑗂��Ă��������Ă��̂ŁA���������������Q�����̂ł����A�������A���Ă���A�Ƃ茾�������Ȃ���n�����A50���N�Ԃ�ɓ������Ɉ����A�Y�����Y�̂悤�ł����B���ň����Ă�������Ȃ������Ǝv���܂��B
�@�J�S�����Ă��܂��āA�V�������Y�ł��B���X�t
�������������C�����ŗ��R�̏H���y���݂Ȃ��炤���ɗ��Ă����������̂ɁA���傤�ǎ������͗���Ń��N�ƃn�i���i�����Ă��B�\����Ȃ���������Ă��܂����B
�I����1�s�͐������v�邾�낤�B�J�S�Ƃ����̂͗�������u��Ւ��苳���v�̂��ƂŁA�Q���\�����݂������2�{�������Ƃ��ŁA�m�荇���̑������u�������v�Ǝc�O�����Ă���B�������AA�搶�A���꒬��Y����E�E�E�B���C�̓ŁB
�������͎�Î҂��I�Ԃ̂����玄�̐ӔC�ł͂Ȃ��̂����A�����Ƃ��u���݂܂���v�Ǝӂ��Ă��܂��B���N���X�ɂł��A�܂��������J�����炢���̂����ǁB
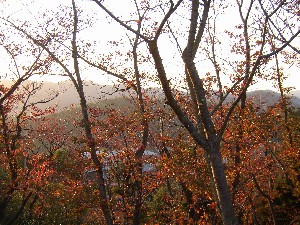 �@�H���[�܂��āE�E�E
�@�H���[�܂��āE�E�E
11��5���i�y�j����@�X�Y�L�A4�C�I�I
�����A�|���|���́u���R�Ԓn�撼�ڎx�������x�v�̔_���ܑ��H���ŁA�Z�����g���炯�ɂȂ��ė[���A���Ă����B
�T�N�ԉ�߂����̉���A���N���Ōゾ�B�c���̈��̐̂���̌Ăі����A�n���҂̖��O���A������Ԓm��Ȃ��ł��낤�|���|�������S�ɂȂ��ē�����5�N�Ԃ́u�{���ɂ����낤���܁v�ƌ����������̂������B
���̂T�N�ԂɁA���̔_���݂͂�Ȃŋ��͂��Ăǂ������ꂢ�ɂȂ����B���낢��Ȑl�̈ӌ����܂Ƃ߁A���R���Ǝ҂ƘA�������A���̕����œ`�B���A�����č����̂悤�ɂ݂�Ȃō�Ƃ�����B
������̒S������Ƃ̑ł����킹��A�H���̊č���E�E�E���̓x�ɏ��ނ����ēd��͂����Ă����B�Q���҂ւ̓������l���Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�C��J���������낤�B
������A�����قڏI���ɋ߂��B
�������_�����g���Ă��邨�����Ő������݂��т��������ꂵ�Ă��ꂽ�Ƃ��ŁA�u�������ς��ŗ[�т͗v��Ȃ��v�ƋA���Ă����B�����āu������ƒނ�ɍs���Ă���v�Ƃ��������Ǝl���\��Ɍ��������B
�W���O�ɂ����A���ė����̂ŁA�u�������ɍ�Ƃ̌�͔��Ă��āA�ނ�ɂȂ炸�ɑ��߂ɐ�グ���낤�ȁv�Ǝv���Ă����B�����͂����ƒx���̂��B
�₨��L�b�`���O�ɐV�������L���o�����̂ŁA�u�����H�v�Ǝv���Ă�����A�ԌɂɈ����Ԃ��ďd�����ɂ܂������Ă����B���̎��4�C�̃X�Y�L�I�I�@���Ⴀ�[�[�B
�Ȃ��45���̊ԂɁA���đ�����4�C�����������̂��Ƃ����B����Œނ��Ă����l���тт��Ă����������B
2�C���R�ł������Ă������A�V�����̏�ɐQ������ƃs�`�s�`�����Ă����B
���ꂩ�炪��ρB�Ƃɂ��������̂悤�ɂ܂�����B�����̂Ŏ��ɂ������A�Ȃ�Ƃ������ɋ�����Ƃ�A�①�ɂɓ���Ȃ��̂ł����݂Ȃ���ɂ����悤�Ƃ������ƂɂȂ����B
�|���|���͈�ԑ傫��71�����A3.1�L�s�̂������āA�܂��o�����čs�����B�����낤���܁B
���͎l���\��߂��ɏZ��ł��钆�w���̋����Y�N�ɁA�u�X�Y�L���ނ�Ă���炵����v�Ɠd�b�B
�e���r�ł����Ă����̂��������肵�����œd�b�ɏo�������Y�N�A�����܂��������킸���āu���肪�ƁB������s���Ă݂邯��I�v�B
��x�������Y�N�e�q���u�ނ�Ȃ������v�Ƃ���ė����̂ŁA�Q�Ԗڂɑ傫��60�����A1.6�s����C�������B
���Ȃ݂Ɏc��2�C�̃T�C�Y�́A53�����A1.2�s�ƁA50�����A1.2�s�B�قړ������炢�������B
�����Y�N�ƃ|���|���͒����ԂȂɂ��^���ɘb���Ă����B�}��`������A���A�[�⒪�������Ȃǂ������Y�N�Ɍ����Đ������Ă���B�ǂ����X�Y�L�̒ނ����`�����Ă���炵���B
�����ŐH�ׂ镪�Ƃ��ߏ��ɂ����镪�ɂ��ẮA���������Ƃ��ė①�ɂɓ��ꂽ�B
�����A���h�g�A���j�G���A����g���Ȃǂɂ��ĐH�ׂ悤�B���������A�A���͂��`�ɐ����̂��B�j���������ς����邵�A�v���Ԃ�ɃX�Y�L�̂��y���������������B
 �@�X�Y�L4�Z���@
�@�X�Y�L4�Z���@ �@���������Ȋ�
�@���������Ȋ�
11��4���i���j����@���ׂ����̂́A�F�B
���x���A���̐e�F�A�b�R����d�b���������B�������݂ŁA���i����킢�킢���C�Ȏq���悯����[��[�����ł���悤�Ȋ��������B
�u�����A�m�g�j�z�[���֍s���Ă����B�������������A�|���|������̎ʐ^�A�m���ɋ��܂��ďo�Ă���B�ʐ^�B���Ă�������ˁB�R�����g���ʂ��Ă�������ˁB�ł��A�����������ēǂ߂�B���[�y�œǂނ���A�����Ă�B�����H�v
��J���ēǂ�ł��邵�ǂ���ǂ�̂܂܁A���T������̕]��ǂݏグ�������B
�Г�1���Ԃ������Ċςɍs���Ă��ꂽ�����ł����肪�����̂ɁA�����2����s���āA�����͎ʐ^���B���Ă��Ă��ꂽ�炵���B
�Z�����������ɁA�N���F�B�̒U�߂̎ʐ^���ςɂ킴�킴�s���Ă���邾�낤�B�{���ɂ��肪�Ƃ��A�A�b�R�B
�A�b�R�̘b�ł́A�����ʐ^�������ς��������悤�ŁA����Ȓ��Ń|���|���̎ʐ^�́u�߂���V���v���Ɍ������v�Ƃ̂��ƁB
���T������̑I�]�̓|���|�����\�z���Ă����ʂ�A���Ɖe��]�����Ă����B�����āu���I�ȍ�i�v�ƁE�E�E�B
�����āA�d�b���ŏ��Ă��܂����B�m���ɂ���́A�|���|���̎ʐ^�̓������Ǝv���B
���N�A��l�Ō��W���ςɍs�������A���܂��܊ӏ܉������Ă����B�x�e�����̎ʐ^�Ƃ����������̂ɂ������āA���낼��ƏW�c�������Ă����B
����|���|���̎ʐ^�ɋ߂Â��Ă����̂ŁA���ƌ����̂��Ƌ����ÁX�Ŏ��������ĂĂ�����A�u����͉����Ⴈ�H�@�@���Ɏ��Ă���Ȃ��v�Ƃ��Ȃ�Ƃ������Ă����B
�ςĂ����l���݂�Ȃ�����������āu��[�H�v�ƍ����Ă���̂ŁA�ӂ��o�������ɂȂ��āu���Ă����Ȃ��āA�@������v�ƂԂ₢���B
���W�͂��ꂼ��e�[�}���Ƃɂ܂Ƃ߂Ďʐ^��W�����Ă���B�Ղ�̎ʐ^�A�C�O�̎ʐ^�A���i�ʐ^�E�E�E�Ƃ����ӂ��ɁB
�|���|���̎ʐ^�͖���A�ǂ��ɏ��낤���Ɩ������̂���ɂƂ�悤�ɓ`���̂��B�u���[��A���̎ʐ^�͂ǂ̃O���[�v�ɂ������A�ǂ����傤�H�H�v�ƍ����āA�Ō�ɂƂ��Ă����悤�ɏ����Ă���B����I
�A�b�R�͍������ɂ��ꂳ��̉��ŁA������ɋA��ƌ����Ă����B30���̒a�����A�悩�����炤���ł��j�����悤�B���[�y�őI�]��ǂݏグ�Ēm�点�Ă��ꂽ�A���ӂ����߂āE�E�E
 �@�����̉Ԃ�����B���O�̓z�g�g�M�X�B��D���ȉԂł��B
�@�����̉Ԃ�����B���O�̓z�g�g�M�X�B��D���ȉԂł��B
11��3���i�j�܂��@�̊�
�[���A�Ђ������т𐆂��Ă��ׂ̂����ɓ͂�����A�u�L���R�����ɂ�������ʐ^���f�C�T�[�r�X�Ɏ����Ă����Č�������A�ق�A����Ȃɑ傫�����Ă��ꂽ�v�Ə����Ă����B
����10��24���́u�ʐ^�v�̂Ƃ���Ŏg�����̂Ɠ����A�Ԗ��ԉł̎ʐ^�������B
�ƂĂ��C�ɓ����Ă���Ă��āA�Ă�������5�����܂�ċA���Ă����B���ł��炦��̂͂��ꂵ�����B���ւցA���̎ʐ^�̘r���܂炶��Ȃ��ł���A�ƃ|���|���Ɏ����������Ȃ�B
�|���|���͎�d���W�Ɍ����āA�̊�Â���B
���`���[�h�v�l�̍��m�̃}���V�����Ɏf�����Ƃ��A�ƂĂ����Ă��Ȗ̊�ɂ��َq���ďo���Ă����������B
���͂����Ƃ��̊킪�S�Ɏc���Ă����̂��B��P����̖{�����Ă��A�̊킪�o�Ă���B
������������肵�āA�|���|���ɂ˂��葱���Ă悤�₭�����B
���낢��ȃ^�C�v�̂�����Č����Ă�����ẮA�u���[���A���[���v�ƌ����Ă���B���������̐l�͖{���Ɋy�B
���̂Ƃ���A���̓t���[�n���h�̌`���������낢��M���C�ɓ������B����Ɏ���������t�����l���邾���ŁA�킭�킭�y�����Ȃ�B
���͓���搶�Ƀv���[���g����o�b�N������Ă���B����ς�u�ԁv�����`�[�t�ɂȂ����B
�Ȃ��Ȃ��C�ɓ�����̂��o����͓̂���B��������鑤�ɂ܂��ƁA��ς���������B
 �@���₫�͖{���ɖؖڂ����ꂢ
�@���₫�͖{���ɖؖڂ����ꂢ
11��1���i�j����@�h�N�̓]�E
�����I�Ȃ��Ƃ��A3���������B
�܂��A�����Ԃ̓���搶���A�u�́[�ƁE�炢�ӑ��v�����f���ɂ����z������ăv���[���g���Ă����������B
�̉ƁA���̎R�X�A��̑��Ԃ����E�E�E�A�u�́[�ƁE�炢�ӑ��v�̐��E�����̂܂�ܕ`����Ă���B�u���ꂪ�����Ԃō���Ă���́H�I�v�Ƌ��Q�����B
�����Ŕ����Ȃ��A���E�Ɉ�����̃X�e�L�ȍ�i�����肪�Ƃ��I�@�ƕ�ɂ��܂��ˁB
�Q�ڂ́A��钷���d�b�����ꂽ�j����̍ēx�̓d�b�B
�̒��������āA�a�@�ɍs���Ă������̌��ʂُ͈Ȃ��ƌ�����B�ł��A�{���ɖ����h���āA�ǂ������Â��Ă����Ƃ���͂Ȃ����낤���H�E�E�E�Ƃ������k�������B
�����ƃX�g���X���������ƁA�j�����������v�����B�������������Ȏ��ẤA�����̐��������Ŕ��f���Ă�������Ȃ��B
�u�C���̋C�y�搶�ɓd�b���Ă݂āB�����Ɛf�Ă������邩��v�ƏЉ���B
�����C�y�搶�ɓd�b������A�������������ɐf�Ă����������Ƃ��B���N�Y��ł����̒��̈������A�u���̍ہA���Ƃ��悤�v�ƌ����Ă�������������B
�u�A��̎Ԃ̒��ŁA�ЂƂ�łɗ܂�����Ă����E�E�E�v�Ƃj�����ꂵ�����ɕ��Ă����̂��āA�����S���炤�ꂵ�������B
�����ȑ̒��̈����́A�Ȃ��Ȃ����l�ɂ͗�������Ȃ����̂����ɁA�{�l�ɂ͖{���ɐh�����̂�����Ǝv���B
���������s����Y�݂��~�߂Ė����Ă���C�y�搶�́A�܂��Ɂu�l���~���v�d�������Ă���̂��Ȃ��B�{���ɂ��肪�����B
�R�ڂ̓|���|���̐e�F�A�h�N�̓]�E�B
�h�N�̓|���|���̏��w����̓������B�T�b�J�[���̃L���v�e���ƕ��L���v�e���Ƃ��ăR���r��g��ł��������ŁA���Z�ł͓����N���u�`�[���ŃT�b�J�[������Ă����������B
�����ɂ���x�V�тɗ������Ƃ����邯�ǁA���i�̓|���|���Ƃ͐����B�����ȃ^�C�v�̐l�Ɍ������B
��w�𑲋Ƃ��ĉ�Ђɓ���A���Z���ォ��������Ă��������ƌ����B3�l�̎q�ǂ�������B
�h�N���������Ђ����߂čD���ȓ��ɐi�݂������Ă��邱�Ƃ́A�����ƑO����|���|���ɕ����Ă����B
����ȑ��k�̃��[�����͂������Ƃ��������B���̓x�Ƀ|���|���Ɓu�h�N�͉ʂ����Ăǂ����邾�낤�v�Ƙb��ɂ̂ڂ��Ă������A��͂�q�ǂ�����̂��Ƃ����邵�A������̗����������邩�ǂ����A���ݐ�̂͗E�C�����邾�낤�E�E�E�Ɠ�l�Řb���Ă����B
�������ɁA�u�]�E�����܂�܂����v�̃��[���B���������ǁA�u�Ƃ��Ƃ�������ˁ[�I�@���߂łƂ��v�Ɗ��������B
12������A�����ƑO���疲���Ă��������̐E�l�Ƃ��ē����������B
�u�傫�Ȍ��f�ł����B�o�ϓI�ɂ��d���I�ɂ���ςɂȂ邯��ǁA���Ƃɂ͈����܂���v�u��l�̐������͂�����݂ɂȂ�܂��B������܂��v
��l�Ƃ����̂́A�|���|���ƃJ�i�_�ݏZ�̂s�N���B�����Ȃh�N�ɂƂ��āA���R�ɂ�肽�����Ƃ��т���l�̐������͂ǂ��f���Ă���̂��낤�H�@�Ɖ��x���v�������Ƃ��������̂ŁA�Ȃ�炩�̗�܂��ɂȂ����Ȃ��Ɖ��߂Ďv�����肵���B
�u���x��Ƃ��͐E�l�ł��v�̈�s�ɁA�h�N�̂��������������ӂƊ�]���������B
�����u�́[�ƁE�炢�ӑ��v�̑������A�h�N�ɂ��肢�����������悤�ȋC������B
 �@��͂��܁A�l�R�W�����V�������ς�
�@��͂��܁A�l�R�W�����V�������ς�
2005�N10���̕�炵
10��31���i���j����@�D���ȋG�߁A�D���ȐH�ו�
10���������ŏI���B�����ς炸���Ȃ��Ȃ�悤�Ȃ����G�߁B���R�̒��ɏo���������A���ɂ��o�����E�E�E�Ǝv���Ȃ���A�d���Ɖƒ�ƃ{�����e�B�A�𑱂��Ă���B
��͐Ԃ��p�C�i�b�v���Z�[�W�Ǝ��̃A���W�X�g�Z�[�W�A�����T�L���[�V����������B���ڂ��ň�����}���[�S�[���h�ƃR�X���X�������炢�Ă���B
�H����ƂĂ����������āA�����ӂƖ����ł�����͂Ȃ��B
�j���j�N�����Ղ�̖���u�߁A�������������肽��ۓ�₿��炪�l�C������B
���Ԃ��ōŌ�̎��n�ɂȂ邾�낤�ȂƎv���A�Ė�̃i�X�ƃs�[�}�����H�ׂ��B���͂����H��ɂ��Ȃ�Ȃ��̂����ǁA�u�����Ԃ��肪�Ƃ��v�̋C�����ł����������B
��ԍD���ȐH�ו��́u���сv�B��ԂɍD���ȐH�ו��́u��v�B�O�Ԗڂ́u�ʕ��v�B
�E�E�E�N���ɕ����ꂽ�炻�������悤�Ǝv���Ȃ���A�N�ɂ�������Ȃ��̂ŕւ�ɏ������B
 �@�E�b�h�f�b�L���̃Z�[�W�̉Ԃ����q���}����
�@�E�b�h�f�b�L���̃Z�[�W�̉Ԃ����q���}����
10��24���i���j����@�ʐ^
���ƂƂ����������𒅂��̂́A�l�N�̌������ɏo�Ȃ��邽�߂������B
���Ƃ��̎q�ǂ��ɂ�����l�N�́A�Ԃ����̎�����悭�m���Ă���B��l�ł����ɂ����x���V�тɗ��āA���ς��Ԃ�����Ă����̂�����̂��Ƃ̂悤�Ɏv���o����B
���邭����₩�ɁA�����̌��t�ł�������ƈ�������N�ɐ������Ă��āA�{���ɂ��ꂵ���B
�l�N�������ɂ����邨������A������́A�����̂����ׂɏZ��ł���B��l�Ƃ��o�Ȃ���̂��낤�Ǝv���Ă�����A�Ԉ֎q�ňړ����Ă��邨����͌��Ȃ��ƌ����B
�c�O���B�����ł���Ȃɂ��킢�����Ă����l�N�̐���p�������Ă�肽���̂ɁE�E�E�B
�f�W�J���ł�������ʐ^���B���āA���̒������^����ɂ�����Ɏ����čs�����B�p�\�R���͂���Ȏ��{���ɕ֗����B
�v���̂����ʐ^�͂��Ƃł����Ɠ͂����낤�B���̏ꍇ�́A�Ƃɂ�����������������ɂl�N�̐���̌������̎p��͂��邱�Ƃ���ԁB
�Ă̒�A������͋����Ȃ����B�C��Ȑl�����A�������u�s���Ă����v�ƌ����ďo�������A1�l�ŋ����Ă��܂����ƌ����B����Ⴛ�����낤�ȁB���C��������A�o�Ȃł����̂ɁA�������������낤�Ȃ��B
�x�b�h�ɐQ������̂�����́A�����ƈ�����ʐ^�߂Ă邱�Ƃ��낤�B
�����p�ʼn����E�������A�����Ԃ�Z�����ʐ^���B��܂�����B���v���o���Βp���������B
���i�̓|���|���ɂ܂��������肾���A�|���|���������炱��������ʂ����������A���O���ŎB�邾�낤�ȁE�E�E�Ƒz�����Ȃ���B�����̂ŁA���������p�͖Y��Ă��イ����ɔ�������悤�Ƀ����Y���\������A�l���݂ɂǂ�ǂ�����Ă������B
���悤���܂˂����A���̊Ԃɂ��|���|���̎ʐ^���A���ɂ����荞�܂�Ă��邱�Ƃ��m�F�����ł����Ƃ������B
 �ƂĂ�����₩�Ȋ����I�Ȍ������������B���߂łƂ��A�l�N�I�I
�ƂĂ�����₩�Ȋ����I�Ȍ������������B���߂łƂ��A�l�N�I�I
10��23���i���j����@�@�R�X���X�Ղ�
�u�́[�ƁE�炢�ӑ��v�̑O�𗬂�Ă����́A��������Ƃ����B����̊C�܂ŗ���Ă���B
���̐�̗����3�̒n��A�n�ׁA��V���A�k��ŋ��͂��āA30���̓��j���Ɂu�R�X���X�Ղ�v���J�����B
9���ɍ���56�����̔n�ד�����ɏW���B�����ɎԂ�u���āA6�L�������Ĕn���w�Z���S�[�����B
���̓��̓L���R�������ʋ��Ă��铹�B�쉈���ɂ��˂��˂Ƒ����ׂ������B
�����傤�Ǔc��ڂɎ������R�X���X���Ԑ���B�Ԃő����Ă��C�����������B
���T�́A���߂Ȃ���E�H�[�L���O�Ƃ����킯���B
�S�[���̏��w�Z�ɂ́A10��30������n��̔_�Y���⋽�y�����̏o�X�����ԁB�����́u�Ƃ�߂��v��u�c�ɏ`�v��H�ׂāA�n�ׂ̂̂�т肵�����R���y����ł��炢�����B
�����͂e�l���W�I�́u�́[�ƁE�炢�ӑ��ւ�v�ł����m�点�������B
 �@�́[�ƁE�炢�ӑ��̂����O�̓c���
�@�́[�ƁE�炢�ӑ��̂����O�̓c���
10��22���i�y�j����@�����̋G��
���[�ƂĂ��������Ȃ����B����Ȃɏ����������Ă������̂ɁA�G�߂͊m���ɏ���B
�v���Ԃ�ɒ����𒅂��B�������������́A��͂蒅���͒������Ȃ��B
���݂�t���ւ��Ă���Ƃ���ցA��������āu�L���R����A�G�̉��ɕ~������ŁA�ҁ[��ƐL���Ă���D���̂�v�ƃA�h�o�C�X���Ă��ꂽ�B
�����A���������̂̐l�ɂ͓�����O�̒m�b���A���̎������ɂ͎p����Ă��Ȃ��Ȃ��B�P�Ɏ����������m��Ȃ�����ǁB
���̎q�ǂ������ɂ́A�����Ǝp����Ă��Ȃ��B���߂̂����ݕ���A������Ȃ��q���قƂ�ǂł͂Ȃ�������H
���̎q�ǂ��̍��́A�N�Ɉ�x�̒����̒��������ƂĂ��y���݂������B
��͂قƂ�Lj���������āA�^���X�̒������L���Ċ����A�܂�������ł��܂����Ƃ�����Ă����B
�������ʂ̒����ŁA���Ȃ�Z�����J���������̂ŁA�����������N��`�킳�ꂽ�B
���O�̎��̂Ȃ������U�����o�Ă�����A�q�ǂ��̖ڂɂ���������̉œ���ߑ��߂���̂́A�N�Ɉ�x�̒��������炢�����Ȃ������̂��B
���A1�l�őS�����������悤�Ƃ���ƁA���Ȃ��ρB���A��������������Ă��I���Ȃ��B
�����玄�́A�����������ɂ������Ă�邱�Ƃɂ��Ă���B
�܂��������i�͊J�������Ƃ������������i�ꂪ���œ���̂Ƃ��Ɏ��Q�������j�̒����J���A���C���܂̂̎��Ȃǂ�����ʂ��B�܂��ӂ���Ƃ��Ă����悤�ȋC�����āA�I���Ɩ�����������B
 �����̃o���^������A�u�������͉A�����Ɂv�Ƌ����Ă��������܂����B���ӁI
�����̃o���^������A�u�������͉A�����Ɂv�Ƌ����Ă��������܂����B���ӁI
10��20���i�j�����@�N�b�L�[�ƃ��[�v���V���b�v
�d���̋A��Ɍ����A�ƂĂ����ꂢ�������B
���F�̋�ɁA�s���N�̉_��������ŁA�o�X�e���J���[�̋B
�R�͍����V���G�b�g�ɂȂ�A�ƁX�ɖ����肪�Ƃ���ƁA�����w���̐��E�ł���B
�a������100�~�V���b�v�Ɋ������A�����N���X�}�X��F�ɏ����Ă��ċ������B
�u�͂�[�[�A10������N���X�}�X���B���N�����Ɓ��������Ď����ɓ������̂ˁv
���������N��������o�����Ȃ��B������N�������B
���̑O�R�N���̂n����A�N�b�L�[���Ă��Ď����Ă��Ă��ꂽ�B
�Ƃ��Ă��������������̂Ń��V�s�𗊂�ł�������A�������ڂ��������Ď����ė��Ă��ꂽ�B
�u���b�N�N�b�L�[�v�Ə����Ă��������A���́u�n�����N�b�L�[�v�ƌĂ�ł���B
�R�R�A�p�E�_�[�Ƃ���݂������Ă���B�R�R�A�p�E�_�[�͎�ɓ���Ȃ�������A�~���N�R�R�A�ő�p���Ă����܂�Ȃ��B���������Ȃ�ƕ��ʂ������ς��Ă��������E�E�E�Ɨ����̕��ʂ������Ă���Ă��āA�u�Ȃ�čs���͂����S�Â����v�Ɗ��S���Ă��܂����B
�_�˂̗��e�������J�i�_�ɍs���Ă��āA���y�Y�̃N�b�L�[�ƃ��[�v���V���b�v�𑗂��Ă��ꂽ�B
�V���K�[�R�[�g�ŕ�܂ꂽ�N�b�L�[�͂����ɂ��������ɂȂ�A���[�v���V���b�v�̂ق��͍����Ă����p���ɂ��ĐH�ׂ��B
�������������I�@�u�����������Ƀ��[�v�������邾���̂��Ƃ͂���ˁv�Ɠ�l�ł��Ȃ����������B�������ɐH�ׂ悤�B
�N���X�}�X�ɂ͎������N�W���W���[�}���N�b�L�[���Ă��B�c���[�ɏ���̂ŁA�ɗ̓o�^�[�͎g��Ȃ��悤�ɍd���Ă��̂�����ǁA���N�͂��������D��̃N�b�L�[���Ă������ȁB
 �@��Ȃ�ƂȂ���������[�X���N���X�}�X���ۂ��Ȃ���������E�E�E
�@��Ȃ�ƂȂ���������[�X���N���X�}�X���ۂ��Ȃ���������E�E�E
10��18��(��)�����@�H�̈�������m�s��
������č��m�s�ցB�Q����������������ǁA�������������猧�W�����āA��Ւ����Ƃ̗m�q����̃A�g���G�ɂ����ז����āA�Љ�Ă�������M�������[�i���ŐH�����āE�E�E�ƁA�߂����ς��L�Ӌ`�Ȏ��Ԃ��߂����ċA����B
��������H�B�{���ɋC�����̂����G�߂ɂȂ����B
�m�q����͎�d���W�Ɍ����Ă��������i������Ă��āA�����Ă����������B�z���܂�̂悤�ȃA�g���G�ŁA�D���Ȃ��Ƃɖ����ɂȂ��̂́A�ō��ɍK���ȓ��X�Ɍ�����B���Ԃ��������Ɨ���Ă���B
����͗m�q����̐l����������Ȃ��B��e�͂̂���X�e�L�Ȑl���B
�Ηj���ɂ̓M�������[�i���u�n�[���F�X�g�v�ŋ������s���Ă��邻�����B�u���Ђ����ɂ��s���Ă݂Ă��������A�d�b����Ă����܂�����E�E�E�v�Ƃ������ƂŁA���߂čs�����B
�A�b�g�z�[���ȃM�������[�i���ŁA�u�L���R����? �m�q�搶���畷���Ă܂��v�ƌ}���Ă����������B�I�[�i�[����Ƃ������萷��オ���āA2�K�܂ňē����Č����Ă�������B
�܂��������s���āA���낢��Șb���������B�I�[�i�[����́u���ɏo�����v�ƌ����̂ŁA�u�ǂ��ɍs��������ł���?�v�ƕ�������A�u�����S���v�B
���C��������X�����炫���ƈӋC�����������B
 �@�Ŕ̌��ɏ����������Ă���̂��I�[�i�[����
�@�Ŕ̌��ɏ����������Ă���̂��I�[�i�[����
10��16��(��)�����@100�L������!

���Ɏl���\�E���g���}���\��100�L�����������܂����B
�{���ɂ��߂łƂ�!
����[�A�{���ɒ�����������ł����B��5��30���A�܂��Èł̒����X�^�[�g���āA12����53�����葱���A�[�����Â��Ȃ��ăS�[�����܂����B
�����������Ȃ��ł���ˁB�����̂��߂ɁA�������������A�����Ă̂��Ȃ��ɂ������đ��肱��ł������Ƃ��A�����ɂȂ�������ł���ˁB
 �@�o���O10��(�r�������̂͊�����̃X�g�b�L���O�ł�)
�@�o���O10��(�r�������̂͊�����̃X�g�b�L���O�ł�)
�X�^�[�g�O�́A�|���|���ɂ͒�����������Ƌْ����Ă��܂����B���Ȃ�̃v���b�V���[�������Ǝv���܂��B
�������߂����C�����ƁA�̂ɂǂ�Ȉٕς��N���邩�z���ł��Ȃ��s���B�u�����Ă݂Ȃ��ᕪ����Ȃ��E�E�E�v�Ƃ����C�����������̂ł��傤�B
 �@50�L���̔��Ƃ̒������B
�@50�L���̔��Ƃ̒������B
40�L���̏���̑勴����50�L���̔��Ƃ̒������B�ӊO�ɂ����̑O�������Ȃ肫���āA�u�_�������m��Ȃ��v�ƕs�������������ł��B�u���[��A�����v�Ƃ����\��ł��B
�����ɂ̓|���|���̎ʐ^���Ԃ��w����Ă���Ă��āA�u��������Ă���v�ƕ����M���ق��̒��Ԃɂ��b���đ҂��Ă��܂����B
�u�����̗��ɋ����قǂ͖�������Ȃ�[�v�ƁA��y�������܂���ċ���Ă��܂����B
 �@62�L���̃��X�g�G���A�u�J�k�[�فv
�@62�L���̃��X�g�G���A�u�J�k�[�فv
�J�k�[�قɂ͒��X�^�[�g���ɗa���Ă��������ւ���C���O�����ē͂��Ă��āA����Ƌx�e���Ƃ�܂��B
�������s�[�N�ŁA�҂��Ă���Ƒ����u�����v��A���B�A�i�E���X���Ђ�����Ȃ��ɁA�u���Ȃ�C���������Ȃ��Ă��܂��B�������\���ɂƂ��Ă��������v�ƌJ��Ԃ��Ă��܂����B
��2�t�A�X�|�[�c����1�t�A���X�`�A�o�i�i�A���ɂ���1�H�ׂāA�����ŏ������Ă����G�l���M�[���⋋���A�����Ƌx�e�������C������U���悤�ɍăX�^�[�g���܂����B
�����Ń��^�C�A��\���o��l���A���l�����܂��B�x��ł��܂��ƁA�����オ��̂ɂ��Ȃ�̋C�͂�K�v�Ƃ���̂ł��傤�B
�|���|���́u�E���g���̃X�^�[�g�́A62�L�����炾�v�ƁA���ƂŊ��z�����炵�Ă��܂����B
�Ђ��͎ʐ^�̂悤�ɁA�e�[�s���O�̏ォ�玝�Q���đ����Ă����T�|�[�^�[��t���A���X�g�G���A�Œɂݎ~�߂�1�x�������݂܂����B
�ł��A�ɂ݂��ǂ�ǂ�Ђǂ��Ȃ邱�Ƃ͂Ȃ��A�ɂ��Ȃ��Ă��܂������܂��āA�Ȃ�Ƃ������������邱�Ƃ��ł��������ł��B
����͑����A�����b�����Ă����̂��Ǝv���܂��B
���ہA���x���u�_�������m��Ȃ��v�Ǝv���������ł��B
�ł��A���̓x�ɂ��낢��Ȃ��Ƃ�������ł��āA�f���̉������ƂĂ��x���ɂȂ��������ł��B
�����āA�����̉����B�ʐ^�̂悤�ɖ؉A�ɍ���������������A�ꐶ�����������Ă����̂ł��ˁB

�|���|�����u���肪�Ƃ��[�v�Ǝ��U���ĉ����Ă��܂������A����̓����i�[�ɂƂ��Ė{���ɂ��ꂵ���������Ǝv���܂��B
��������͂����∹��݂���ȂǁA���ꂼ�ꂪ��������Ă݂�ȂŐH�ׂȂ��牞�����Ă��āA�����m��ʎ��ɂ��킴�킴��n���Ă����̂ł��B�������l���͂��ڑ҂̐��_���c���Ă����ł��ˁB
���������������̂́A��������͑o�ዾ�Ń[�b�P�����m�F����l�A����ł��̖��O���m�F����l�A���ꂼ��`�[�����[�N�悭�������Ă���̂ł����A�ȂɂԂ�ɂ��V��Ȃ̂Ŗ���̏����Ȏ��Ɉ��J�B
�������Ă���������āA�u����[�A���ꉽ�ēǂނ�?�v�Ƃ��A������ρB
���̂��������i�[���ʂ�߂��Ă��܂��Ă���A�u�O�d���̃C�g�E���[�[��A�������痈�Ă��ꂽ��ł��ˁ[�B�������!�v�Ƃ��吺�ŋ��ԁB�w�����琺�����������i�[���A�U��Ԃ��Ăɂ����肵�āu���肪�Ɓ[�[!�v�B�ƂĂ����������B
�u�ޗnj��̃X�Y�L���[�[��A���������ޗǂɍs����������܁[�[��!�v�Ƃ����A�l�I?�Ȑ������B
�X�Y�L����͂Ƃ��Ă����ꂵ�����ɁA�u�܂����Ăˁ[�v�B
�]�T�̂��郉���i�[�́A����ŕK���Ŗ��O��T���Ă��邨������ɁA�t�Ɂu���̃t�N�C�Ł[���v�Ǝ����̖��O�������Ď��U��l�������B
��������́u�����Ă��낤���ق����y��v���āB(��)
�u�����̎���������A�͂�ւ���Č���!�v�u�܂����Ǝd�������ق��������܂��v�ƁA�呛���B�m���ɂ��̉����͂��Ȃ�Z�������ł������A�u���Ɉ�l��l�ɃR�����g���l����̂͂������Ȃ��Ɗ��S���Ă��܂��܂����B
�|���|�����������́A�����u������̃|���|������ł��v�Ɖ����狳����ƁA���������u�|���|�����[�[��A�ʐ^���B���邯��A������Ăˁ[�[!�v
�J�����������Ă��������l�^�Ɏg���Ă��܂����B�E�X�ł��B
 �@87�L���߂��A�Ηz��w�ɎāA�Ђ�����O�֑O�ցE�E�E
�@87�L���߂��A�Ηz��w�ɎāA�Ђ�����O�֑O�ցE�E�E
80�L�����߂������́A�{���ɂق��Ƃ��܂����B
���悢��Ō�֖̊�A94�L���n�_�̍��c�̒������Ɍ������đ����p��������܂����B
���̍��ɂ̓����i�[�݂͂�ȁA�����������C���Ȃ��قǔ�J���ނ��Ă��܂��B���ɂ́A�{���ɖ��V�a�҂݂����ɂӂ�ӂ炵�Ȃ��瑖���Ă���l��A�̂���������䂪��œ|�ꂻ���Ȑl�����܂����B
�D�����������i�[�ł����A�Ō��10�L���͑̂��d���A�肪���т�Ă��܂��ă_�����Ǝv�������A�����Ŏ~�߂��牽���Ȃ��Ȃ�Ǝv���đ������E�E�E�ƐV���ɃR�����g���Ă��܂����B
���������S�[���Ɍ������Ĉ���ł��O�i�����Ƃ��郉���i�[�̎p�ɂ́A�l�Ԃ̎���m��Ȃ��s�v�c�ȗ͂̂悤�Ȃ��̂������āA�q�݂����悤�Ȉ،h�̔O���o���܂����B
���͖��N�A���̂�����ŗ܂ł�����ł��܂��B���N���|���|���̌�p��������Ȃ���A�u�������B�����܂ŗ������͂��Ăł��S�[�����邾�낤�v�Ɗ������܂����B
���ۂ́A�Ō��4�L���͈�x�����������葱���������ł��B12���ԑ�ŃS�[���������Ǝv�����ƌ����̂ŁA�т�����B
�S�[���̏u�Ԃ͂��������u���܂��ʐ^���B��邩?�v�Ƌْ����Ă��܂����B
���ɂ��Ă͊�Ղɋ߂��ʐ^�ł��B(��) �͂����Ă�����A�ꐶ�|���|���ɍ��܂ꂽ�ł��悤����ˁB
���͍����A�~�����āA1�l�Ńr�f�I�ƃf�W�J���̗����Ŏʂ��Ă��܂����B
�|���|���́u��������B�l�����ăJ����2����g���̂�����ς���v�ƌ����Ă����̂ł����A��͂肻�̒ʂ�ŁA���������������A�r�f�I�ŎB���Ă����炢�J�����ɂ��邩�Əł邵�A�����{���ɍQ�������������B
�ǂ����Ă��r�f�I����ɂȂ��Ă��܂��Ďʐ^�����Ȃ��̂��c�O�ł����A���̐��������Ȃ��M�d�Ȏʐ^�͂������������ł́u���̎��X�̕\��o�Ă�ȁv�Ǝ��Ȗ������Ă��܂��B
��ԍŌ�ɎB�����ꖇ�́A�S�[�����Ă����������ɂ��ɂ�����p�N���Ă���Ƃ���B���̒B�����ɂ��ӂꂽ�\��ŁA��������͂��߂������܂����B

����A�|���|���͂����������̃��_�������̎�ɂ����Ă���āA�u���肪�Ƃ��A����������v�Ƃ˂�����Ă���܂����B
���͂��ꂩ��A�����i�[���w�����Ă����̑܂����ɁA���ԏ�܂ŎԂ��Ƃ�ɂ������̂ł����E�E�E�E
����Ⴄ�l���݂�ȃ��_�������ă����i�[�ƃJ���Ⴂ�B�u����ꂳ�܁v�Ƃ��u���߂łƂ��v�Ƃ������Ă�������̂ɂ́A������Ɛ\����Ȃ��p�������������ł��ˁ[�B
10��15��(�y)�J�@�@�E�F���J���p�[�e�B�[
�����ɂ��̉J�̒��A�ߌォ���t���̈����^�������ցB
�r���ŏ����̂��߂ɘn�����w�Z�Ɍ������l���\�s�̃g���b�N�ƁA��������������B
�ב�ɂ̓��C�g�₽���܂�ς�ł����B�ߌォ�珀������������Ȃ̂��낤�B
���N�Ȃ���A���N���J�̒��ł��e���g���Ă���I�肽��������B
�Ԃ̃i���o�[������ƁA���ꌧ��ޗnj��̑I�肽�����B
�̈�قŃ[�b�P���Ȃǎ���Ă�����A���傤�lj��c����ƈꏏ�ɂȂ����B
���N�̃E���g���ł�8�ʁA��������\���郉���i�[�̑�H���B
�u������Ă��������ˁv�Ɛ���������ƁA�u���N�͊߂�ɂ߂Ă��āA���邩�ǂ����v�Ă��Ă���Ƃ���v�ƌ����B
���c����̂悤�ȑ�x�e�����ł��A���낢�날��Ȃ��B
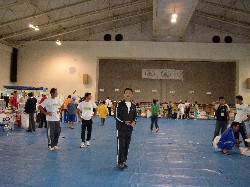 �@��t���ő��X�Ƃ��y�Y���l�̎p���E�E�E
�@��t���ő��X�Ƃ��y�Y���l�̎p���E�E�E
�[��5������A�E�F���J���p�[�e�B�[�B������̑��h���邨��҂��܂Ń����i�[�̋g�c�搶�����������B���N�͑���݂����B���D����ɂ����Ă����B
�������l�l�l�̒��A���Z�̃N���u�̌�y�A�吼�N�ɉ�����B�u������Ă�!�v�u�����A����?�v�u1381�v�E�E�E������100�L���������A�o���ĂȂ����Ȃ��ł���B
�ق��ɂ���d���W�ɉ��l�Ɨ��Ă���Ă���R�{�N�Ƃ��A�����q��m�荇���̐搶�������吨�o�ꂷ��̂����A�S�R��Ȃ������B
�|���|���͂���艮����̂��ǂ��H�ׂāA���͕���ő҂��Ă���ƐC�ۓ���̒|�ւ��Q�b�g���āA30���قǂʼn������Ƃɂ����B
�|���|���̒��q�͂܂��܂��A�ł������Ă݂Ȃ���Ε�����Ȃ��A�Ɩ{�l�͌����Ă���B
���N�����ْ����Ă��邻�����B���N�͉����m�炸�A�킯�������炸�A�܂��������呖���Ă݂邩�E�E�E�Ƃ������̂�C���������B
�ł��A���N�͌o��������Ԃ�A�ǂ�Ȃɑ�ς��g�ɟ��݂ĕ������Ă���B
�͕̂K���ǂ����ɂ��Ȃ邾�낤�B�ς�����ɂ݂��A������Ԃ��A�����Ŕ��f���邵���Ȃ��B
T�V���c�͋��N�̃E���g���̐^���ԂȂ̂𒅂đ��邻�����B
���悢�斾�����A5��30���X�^�[�g�B
 �@�E�F���J���p�[�e�B�[���͈��ʂ�A�[�P�[�h
�@�E�F���J���p�[�e�B�[���͈��ʂ�A�[�P�[�h
10��13��(��)����@��(�Ђ݂��j
�u���͂قƂ�ǖ��͌��Ȃ��v�A�L���R����͂悭���������ď��܂��B
�����ł��傤�ˁB��������ɂ��Ȃ��A�Ƃ����Ƃ���ł��傤���B�x�b�h�ɓ����3�b�ȓ��ɃO�[���Ƃ��B�L���R����͗�Ԃ̒��ł��ǂ��ł��A�����l�ł��B
�������Ԃ����Ȃ������Ȃ̂ŁA�����Ƃ��ɖ����ăJ�o�[����̂��Ƃ��B�������܂ܖ����Ă��܂������Ƃ����邵�A�u�n�������ȁv�Ƃ����f����ςɍs���Ė����Ă��܂��āA�|���|�������Ɂu�f�����������Ȃ��v�ƌ���ꂽ�G�s�\�[�h������܂��B
�u�����ĉf��ςĂ�����A�Ƃ��Ă��C�����悭�Ȃ��Ă��āE�E�E�v�ƌ�����ƁA�t�ɗ����m�ēɊ�ꂽ�Ƃ������܂����ł��B
���āA�O�u���������Ȃ�܂������A�|���|�������������͒������A�u�ւ�Ȗ��������v�Ƙb���Ă���܂����B
�}���\�����ő����Ă�����A���̂܂ɂ��R�[�X���ύX�ɂȂ��Ă��āA��l�ő����Ă����̂������ł��B�����A�ł����ł��傤�˂��B
�u���R�Ƃ��Ă��邯�ǁA�������ɂ�͂�S�̂ǂ����ɕs���������āA���ꂪ���ɂȂ����̂�B�v
�L���R����̖����͂ł����B
���悢��E���g���}���\�����߂Â��Ă��܂����B�S���̃����i�[�������A�C�����͎l���\�ɂƂ�ŁA�ו��̏��������Ă��邱�Ƃł��傤�B
�|���|�������̃[�b�P���́A1381�Ԃł��B
10��9��(��)�܂�@�C�ӂ̊y��
���U�������������āA�C�ӂŕ������͂�ł̂��H����A�ƂĂ��y���������B
�I�J�_�����ƁA���C����A����҂��܂̃q���V����(�|���|���Ɠ����A�����������A�C��삪��D���Ȃ̂�����!)�A�������v�w�B���ΖʂȂ̂ɁA�܂�Ő̂���̗F�B�̂悤�ɂ킢�킢�B
�C�ɐ����Ď��������̃n�}�O���A�����Ő������G�����сA�I�J�_���v�Ȃ̂������̂�������C���A�q���V����̃I�[�X�g�����A�y�Y�̃w�l�V�[�A���̏�ɋ߂��Œނ��Ă����n���̐l���A���2�C���������Ă����Ԃ̏�ŏĂ����B��͖Ԃ̏�Ńs�`�s�`���˂Ă�������ˁB
�Â��Ȃ��ăI�J�_����̃��B���ɂ��ǂ��Ă�����A����̃f�U�[�g�����������Ȃ���A�܂��킢�킢�킢�B�b��͂Ƃǂ܂�Ƃ��낪�Ȃ��B
���������q���������ǁA�C�ӂ������낷���߂͍ō��B�x�b�h�ɉ���������܂܁A���z�[�������߂���̂��Ƃ����B
�o���ŕ�炵�����Ƃ̂���I�[�i�[�̎���A�����ȂƂ���Ő�������Ă��ĂƂĂ��X�e�L�B�Ȃ��ʐ��E�݂����ȊC�ӂ̊y���������B
 �@�����͓y���h�̂������B�傫�ȃe�[�u���Ƀo���̃����`�����}�b�g���X�e�L�B
�@�����͓y���h�̂������B�傫�ȃe�[�u���Ƀo���̃����`�����}�b�g���X�e�L�B
10��7��(��)����@���W�Ə���W�i�Ђ݂��j
�������獂�m���W���J���ł��B
�L���R���A�u�N�Ɉ�������A�|���|���������������N������v�Ə��A�V�����\���������܂����B�|���|�������̎ʐ^�́A���N�����I�ł����B
�ǂ�Ȏʐ^�Ȃ�ł��傤?�@���́u����ہ[�Ɓv�ɍs���Ċς�̂��y���݁E�E�E�Ƙb���Ă�����A���������ςɍs���Ă����l����d�b��������܂����B
�u�����������Ă܂���v�B�݂Ȃ���{���ɐe�ł��B
10��16������́A���悢��NHK�̑S������ʐ^�W���J���ł��B
���m���ɂ́A���N1��5������1��15���܂ł���Ă��܂��B�݂�ȂŊςɍs�������ˁA�Ƙb���Ă��܂��B
����10��30������11��6��������A���������ł��ˁB�ꏊ�́ANHK�������Ǔ�BK�v���U�ł��B
���ɂ�11��12������11��21���BHNK�_�˕����Ǔ��I�[�v���X�^�W�I�ł��B
������12��13������12��24���BNHK�����Z���^�[�X�^�W�I�p�[�N�M�������[�ł��B
���Ƃ͂��[�ƁE�E�E�A���ł�10���̗\��������܂��傤���B
10��16������10��30���A��錧���˕����Ǔ��M�������[
10��17������10��23���A�D�y�����ǃ��r�[
10��26������11��2���A���l����Z���^�[1F��v���U
���߂��݂̂Ȃ���A�悩������ςĂ��������ˁB
10��6��(��)����@�����i�Ђ݂��j
���͂��܁A�L���R����̍D���Ȕ����̋G�߂ł��B
�X��17���Ɏ펪�����āA�����H�ׂ���̂�����A����Ė{���ɂ����ł��ˁ[�B
�v�����^�[�ł����ł��A�Ƃɂ����y��������Ζ����ĂĂ݂邱�Ƃ��I�X�X�����܂��B
�肪�o�Ĉ���Ă����y���݁A���n����10���������Ȃ������ɐH��ɏ悹�邱�Ƃ��ł���V�N�Ȃ��������A���܂��ɉԂ��y���߂�B
��̉Ԃ��߂ł�̂́u�́[�ƁE�炢�ӑ��v���炢�����Ȃ��̂���(��)
�Ԉ����Ȃ���H�ׂ锲���́A�_�炩���ĐX���Ă��āA���ł����Ђ����ł����ł����������B
�M�X���т̏�ɏ悹����A������������Ȃ��Ƃ��������ł��B
 �@�[���̒�B�L���R����͋A���Ƃ����u�ǂ��������?�v�ƌ����ł��B
�@�[���̒�B�L���R����͋A���Ƃ����u�ǂ��������?�v�ƌ����ł��B
10��5��(��)�J�@�C��
�u�C���v�̃I�J�_����A�u�͂��߂܂��āv�̃��[���������������B�Ƃ��Ă����ꂵ���B
�Љ�Ă����������̂́A���C���B���肪�Ƃ��B
�y�������s�ɏZ��ł��āA���R��אl�Ƃ̋������R���Z�v�g�Ɂu���n��v�������߂Ă�������B
���C����I�J�_����̘b�����Ƃ��A�u����[�A�������Ƃ悭���Ă���v�Ƃт����肵�����̂��B�������A�����炱�����C������Љ�Ă����������킯���낤�B
���������Əo��Ƃ�������l�����E�E�E�Ȃ�ƂȂ�����ȋC�����Ă����I�J�_�������̂��B
�܂��A�l���̃e�[�}�������u�L�������ĉ����낤�v�B
���R�ɖ������Ɗ�����S���A���R�ƈ�̉������z�^�̃��C�t�X�^�C�����A���R�f�ނ̓y���h�̉Ƃ��E�E�E���Ǎ������̂Ƃ��낪����������A���������Ă���͓̂��R���B
�ł��A�X�P�[���̑傫���◝�O�̊m�����A���X�Ƌ�̉�������s�́A�p�\�R���̋Z�p�E�E�E�S���A�������Ƃ͒i�Ⴂ�B
�������Ȃ��A����Ȑl�������߂��ɂ��炵���Ȃ��ƁA���h���Ă��܂����B
�̂�т�u�|���|���v�̎����������ǁA�I�J�_���炢���ς��h���������B
 �@�|���|�����B�e�������̕l�B�I�J�_����̈�����C���B
�@�|���|�����B�e�������̕l�B�I�J�_����̈�����C���B
10��4��(��)�܂�̂��J�@�e�F
��ォ��e�F���A�Ȃ����B�P�l�ő�����ɏZ��ł��邨�ꂳ�A���@�����炵���B
����҂̂P�l��炵�͒������Ȃ�����ǁA���������邩������Ȃ��B����Ă���Ȃ�����S�z���낤�B
�ޏ��Ƃ͒�2�ŃN���X���ꏏ�ɂȂ����B���������ǂ��Ȃ��āA��3�ł������N���X�ɂȂ肽���ƁA2�l�ŒS�C�ɂ��肢�ɍs�����B5�N���X�������̂��B
�O�芐���Ē�3�ł������N���X�ɂȂ������A���ƂƓ����ɑ��ɍs���Ă��܂����̂ŁA�ȗ������Ɨ���ďZ��ł���B
�ł��A�N�Ɉ�x�͂ǂ��炩���K�₵����A����܂ł͒a�����ɂ͍̐������o���̉Ԃ肠���Ă����B���܂�ɂ��{���������Ȃ��Ă��āA�ʂ̂��̂ɂȂ������ǁE�E�E(��)
���邭���C�ŗD�����āA����ׂ肾���Ǝ~�܂�Ȃ��q�ŁA���ނ̐��b�D���B
�ޏ��Ƙb���Ă���ƁA���w���̎����班�������Ԃ������Ă��Ȃ��悤�ȍ��o���o����B
���͖����A�����̒��w�����瑊�k����B���ꂼ��̋��ɂ��ӂ��A�Y�݂�z���E�E�E�B
���͂P�l�Ő��k�͑���������A�ǂ����Ă����������Ă��܂��āA�Ȃ��Ȃ����Ԃ̔z��������Ȃ��Ă��Ă���B
�u�\��Ƃ��Ă��������B�ォ�痈����A���O�������Ă����悤�ɁA�h�A�Ɏ����Ă����Ă��������v
�u������? �a�@�݂�������Ȃ��v�Ə��ĕ��������ǁA��k�Ȃ̂��{�C�Ȃ̂�������Ȃ��B
���A�q�ǂ������̑����́A�u�ق�Ƃ��̗F�B�����Ȃ��v�ƌ����B
������������ɂ������āA�y�������ɏ������Ă���̂ɁA�S����M���Ă���킯�ł͂Ȃ��ƁE�E�E�B�������݂����b�B
���w����ɁA�ꐶ�t�������Ă�����e�F�Ə��荇�����̂́A�����킹�Ȃ��Ƃ������B
10��2��(��)����@�K���[�W�V���b�v�i�Ђ݂��j
�݂�Ȃ̍�i���펞�W�����Ă����A�u�K���[�W�V���b�v�v������I�[�v�����܂����B
�ꏊ�́A���ƍH�[�|���|�����������B�ʓ��ɍH�[��V�z�������ɁA���ꏊ��m���Ƀ��t�H�[�����Ă��܂����B
�������݂�Ȃ́u�K���[�W�V���b�v�v�Ƃ��Ďg�����ƂɂȂ����̂ł��B
���̏����ȊŔ��t���A�Ƃ��닷���ƍ�i�������A���������̃V���b�v�ɂȂ��Ă��܂��B
�܂��܂����ꂩ��ł����ǂˁB�Ƃɂ����X�^�[�g���邱�ƂɈӋ`������̂����B
�����͂������ƁA���q�����[�v���n�E�X�̃P�[�L�������ė��Ă���܂����B
�u�Ђ݂�����A�������n�߂���āA�l�����C�ɂ���Ǝv��Ȃ�?�v�ƃL���R����B
�u���������A���ł������̂�ˁB�q�ǂ������ɂ͉�����D���Ȃ��̂������āA���C�ɂȂ��Ăق����BI�����̌�ɑ����Ăق����v�ƁA�^���Ȋ�ő��q����B
I�����͍��N�́u��P�Q��`�����e�B�[��̎�d���W�v�ŁA��ƃf�r���[���邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B
�r�[�Y��V�R�A�w���v�̃A�N�Z�T���[����邱�ƂŎ��M�������A���X�ƌl�����o���āA�Q������̂ł��B
��l�����݂͂�Ȃ��ꂵ���B�݂�Ȃ�I�����藧�āA�����������Ǝv���Ă��܂��B
�����̂��߂���Ȃ��A�q�ǂ������̂��߂Ǝv���ƁA�悯�����C���o�钇�Ԃ����ł��B
�����āA������E�E�E�Ƃ��Ă��M�d�Ȃ��̂�����邱�ƂɂȂ����̂����ǁA����͂���������ł��b���܂��ˁB
10��1��(�y)����@�X�Y���o�`�ƃS�[�^�}�i�Ђ݂��j
�u�́[�ƁE�炢�ӑ��v�̒�́A���A�H�̎��n�̎����ł��B
�����A�s�[�i�b�c�A�`�A���������A�����A�u�V�����E�E�E�A�I�͏������ꂽ�ʎ����Ȃ̂ŁA������ɍ̂�ɍs���܂��B
����݂�ȂŌI�E���ɏo��������A�傫�ȃX�Y���o�`���Ԃ�Ԃ�P���Ă��āA�����Ȃ��ގU����n���ɂȂ�܂����B
���N�̓X�Y���o�`���ُ픭�����Ă��܂��B���[�Ƀy�b�g�{�g���𗘗p���ĒN����������A�u�X�Y���o�`�ߊl��v���邵�Ă܂������ǁA���ɉ��C���X�Y���o�`�������Ă܂����B
�u�X�Y���o�`�����Ȃ�������A�I���т��H�ׂ�ꂽ�̂ɁE�E�E�v�A���炭�L���R���ڂ₢�Ă��܂����B
����ɂ������т𐆂��āA�݂�ȂŁu���������A���������v�ƐH�ׂ܂������A�����P�l���̒��V(�L���R����̂�������)�����́A�u��т͂܂����v�ƌ������Ă��܂����B
�����Ɛ푈�����v���o���̂ł��傤�ˁB
�L���R����͎G�����т��D���ŁA�����́u�����H�̓X�E�ӂ��v�ɂ��s���Ă��܂����B
�ȑO�A�A�}�����T�X���͔|���Ă����悤�ɁA����Ƃ��Ђ��Ƃ��������������Ă��܂��B
���čؐH����{�ɂ����e�H���A���N�ɂ͈�Ԃ����Ǝv���܂��B
����ɂ�������Ă��܂��̂ł͂Ȃ��A�Ƃ��ɂ͂��������X�ŊO�H�����邵�A�Ƃ��ɂ͎�̂����������邵�A�Ƃ��ɂ݂͂�Ȃŗ�������������ăp�[�e�B�[������B
�E�E�E�Ƃ����킯�ŁA�����͎l���\�s�̃C���h�ƒ뗿���̓X�u�S�[�^�}�v�ɍs���Ă��܂����B
�Ђ����Ɠ��̃J���[�A�i��(�v���[���ƃo�^�[��2��)�A�^���h���[�`�L���A���b�V�[�A�`���C�E�E�`���C�͏������{�l�����̖��ɂ��Ă��܂������A���Ƃ͑S�������B�������������ł��B
 �@��̊킪�X�e�L�ł���
�@��̊킪�X�e�L�ł���
2005�N9���̕�炵
9��27��(��)����@�H�ׂ邱�Ɓi�Ђ݂��j
���ӂ߂����蔧�����Ȃ�܂����B���炵���H�̋L����������A�L���R�����q����⒇�Ԃ������W�܂��āA�{�����e�B�A�̉����܂����B
�v���Ԃ��I���������ꂳ��Ɨ��āA�ɂ��肳��̗F�B�́���������ꂳ��ƎQ�����Ă���āA�킢�킢�B
�Ƃ��Ă�����������̂��܃h���b�V���O�������K���āA�y�����ЂƂƂ����߂����܂����B
�u�t�̐搶�́A���{�������l����B�Ƃт��肨���������X�`���A�����̂Ƃ�����璚�J�ɋ����Ă���܂����B
���͖��̔Z�����̂��嗬�ɂȂ��Ă��邯�ǁA���w���������g��Ȃ��ł���ԂƊ��߂ł����Ƃ�������������̂��{���̖��ȂƂ��������ɁA�݂�Ȃ�����ɂ��ȂÂ��Ă��܂����B
���̂����������ċA���āA��̂�������ƃA�������Ė��X�`�����܂������A�����ł��u��������!!�v�Ƌ���ł��܂����قǂł��B
�������̉�́A�H�ׂ邱�Ƃ��ƂĂ���ɍl���Ă��܂��B�����邱�Ƃ̊�{�ł����̂ˁB
�������ԂƂ����������̂�H�ׂ�̂́A�ق�Ƃ��ɍK���B
���������ӂȂ�����A���������̃R���|�[�g������Ď����Ă��Ă���Ă��܂������A�ԃ��C���Ŏϋl�߂����͑f�l�Ȃꂵ�Ă��܂����B
�L���R����́u�����悭�R���|�[�g����邯�ǁA�ǂ����Ă������̂͂���Ȃɂ���������?�B�����̂����������܂����̂�����v�Ǝ���U�߁B
�u�炪�����܂ςĂ݂āB�ԃ��C�����Y��Ȃ��łˁv�Əڂ����A�h�o�C�X���Ă�����Ă��܂����B
�����������ӂȐl���āA�����ł��ˁB����̐l���K���ɂ��Ă���܂��B

9��26��(��)����@�����Y�ݎn�߂�
����ƌ{�������Y�ݎn�߂��B�����̂��ĂƖ��H�ׂĎY�A���N�ȗL�������B
���낻�납�ȂƎv���āA�|���|���ɋ��̖ؔ��ŗ��Y�ݏ�����t���Ă��炢�A���k��~���ăN�b�V�����ɂ��Ă���Q�������炢�������Ǝv���B
���͎Y�܂��A���k�͂���R�U�炵�Ă��܂��āA�Y�{�܂Ŕ��ɏオ���ėV�Ԃ��܂B
���x�̓������O���X���ۂ��ւɂ��āA���̂悤�ɔ��̒��ɕ~���đ҂��Ă�����A�������킢�������P�A���傱��Ƃ������B
�L�O���ׂ���1�����ʐ^�ɎB���āA�|���|�������������тɂ��Ē��H��H�ׂ��B
�����̒��������ƎY��ł���Ǝv���B�������������т��B
���Ȃ݂Ɏ��͗��������т͐H�ׂȂ��B���̔Ԃ�������A�ʎq�Ă��ɂ��悤�B
 �@�|���|�����p�̒��q�́A�x�g�i�����甃���Ă������C�ɓ���o�`�����Ă�
�@�|���|�����p�̒��q�́A�x�g�i�����甃���Ă������C�ɓ���o�`�����Ă�
9��25��(��)�����@�Ō�̉^����
�n���n���w�Z�ƍZ���������^����������B���N�A�Ō�̉^����Ƃ����B
����10���N�s�������Ƃ��Ȃ������̂ŁA���Ѝs���Ă݂����Ǝv�������A���m�s�ł������ȉ���肠����߂��B
���݂̔n��������y�n�́A�����̔��������B����������������ɁA���w�Z�Ւn�Ɂu�́[�ƁE�炢�ӑ��v���ł����킯���B
������Ƃ����킯�ł͂Ȃ����A���N�^����́u���̕��v�ł́A���͂P�����悭���Ă�B
�u���̕��v�͒n�悩���t���W�߂��Ƃ��ɂP���̕���n����A�����̍Z�����ɎQ�����Ă��炤���߂̍H�v���Ǝv�����A�ܕi���p�ӂ���Ă���̂��B
���A�S���R�O�����炨���i�����A���ٓ�����ݕ���p�ӂ��Ă����āA���͂V���ɍ��m�s�ցB
�[���A�����A�u���N��2���������v�ƌ����āA��펞�̌g�у��W�I��������ċA���Ă����B
������8���Ƃ������ƂŁA�����͎��Ԃ̖�肾�Ǝv���Ă������A����ɂ��Ă��}�������B
����8�N�ɑn���A�������w���������Ƃ���100�l���炢���k�������B
�V���ōZ�̂����債�Ă���ƒm���āA���債����̗p���ꂽ�B
���N��y�������̂��Ă��ꂽ���̍Z�̂��A���N3���ł����܂����ƂӂƋC�������B
���W�ɏ��߂ē��I����60���̗m����A�����̂Ō��փz�[���ɏ����Ă���Ă���B
���̊G�͂ǂ��Ȃ�̂��Ȃ��A����Ȃ��Ƃ������B
�x�Z�ɂȂ�O�ɁA������x���w�Z�ɍs���Ă݂����B�|���|���Ɏʐ^���B���Ă�����Ă��������ȁE�E�E�A����Ȃ��Ƃ��l���Ă���B
9��23��(��)�@����@�@�l���\����J�i�f�B�A���ʼn���
���V���ɉ䂪�Ƃ����ꂼ��̎Ԃŏo���B
���̎Ԃ͐ԓS���̉͐�~�ɒu���āA�|���|���̎ԂɃ����^�������J�i�f�B�A�����悹�č]���ցB
�]���̃J�k�[�ق̉�����l���\��̐ԓS���܂ŁA��l�ʼn��낤�Ƃ����v�悾�B
�Ԃő����Ă�40�L���͂���B��͎֍s���Ă��邩��A�����Ƌ��������邾�낤�B
�|���|���͓����R�[�X�����O�̃t�@���g�{�[�g�ʼn��������Ƃ�����A�u�X���ɏo������ƁA�܂��R����4���ɂ͒����ł���v�ƌ����Ă����̂��B
�Ƃ��낪�A����͖��d�Ȍv�悾�������Ƃ��A���킶����͂߂ɂȂ����B
�J�i�f�B�A���͍L���ĉו�����������ς߂邵���������B���̂����d���Đi�܂Ȃ��̂��B
���͏��߂ẴJ�k�[�B�p�h��������̂������̂��A���܂�ď��߂āB
�Ȃ̂ɗ��K���Ȃ��A�����Ȃ�u����������A������v�ŁA�u��납��E�A���ƌ�������A���̒ʂ肱���ŁB�����꒾���Ă��A��Ƀp�h��������Ȃ��łˁB�p�h���������Ȃ�����A�����ǂ����傤���Ȃ�����ˁv�ƌ����ďo�������B
�]�����o�ĂT�������Ȃ������ɁA�ŏ��̎����������Ȃ肫���B
�}�Ȑ��A�t�����g�B�J�i�f�B�A���͂���ɐ������Ԃ�A���̓p�j�b�N�ɂȂ��ĉE�����������炸�K���ł������B
�|���|���́u���[���A�J���������т����v�Ɣߖ������ĂQ��̃J�������^�I���Ő@�����Ƃ��邪�A���̃^�I�����т���т���B
�h���o�b�N���犣�����^�I�����o���ēn���Ȃ���A����ȋ��|�����x���키�̂��Ƒz�����邾���Ō�����킭�B
���ہA���x����������ė����B���̓x�Ƀ|���|�����s�����ŁA�u�E�A�E!�v�u������������!�v�ƌ��ŋ��ԁB
�����ʂ蔲����Ɓu�������[�v�Ƃ܂����ԁB����Ȃɕv�w�ŕK���ŗ͂����킹��̂́A���߂Ă̂��Ƃł͂Ȃ����낤���B
�������ł͉���ɂ������A���͑̂��k�߂ăp�h���𐅖ʂɂ��Ȃ��悤�ɃJ�k�[�ɗ���ł��܂����B
�悤�₭�p�h���ɂ�����A���͂����n���]�T���ł����B
��͂�삩�猩��l���\��́A�L��!!�@����Ő��ʂ������Ă����Ƃ����̂�����A�̂͂ǂ�قǂ̑�͂��������Ƃ��B
����̑䕗14���̒ܐՂ͂�����Ƃ���Ɏc���Ă��āA10���[�g������̎R�̖X�ɂ�������S�~���Ђ��������Ă���B�M�����Ȃ����i���B
�������������|����Ă�����A���H�̃p�C�v���C�U���Ă���l�����ɂ����x���o������B
���̗F�ނ�����Ă���l�A�Ԃ𓊂��Ă���l�ɁA�u����ɂ��́[�A���N�͂ǂ��ł���?�v�u����A����܂肨���˂��v�B
�����Ȑ싛�͂����ς��������A���ʂɂ҂��҂���яオ���Ă��鋛�������B
���c�̒������̂�����ł́A�ڂ���j���ł����B�C���炱��ȂƂ���܂ŏ���Ă���̂��B
�������̂��тɁA�|���|������납��ʐ^���B�����B
���̏ォ��͒����ʐ^����̃|���|���̎ʐ^����3�l���A�����Y��������B
�g�тł����ƘA������荇���Ȃ���A�u���A�����B����������Ԃ̒������v�Ȃǂƒm�点��ƁA�������ɍs���ăJ�����A���O�������߂đ҂��Ă���B
��̑O��������A����Ȃ��Ƃ͂ł��Ȃ������낤�B�g�т͂�͂�֗����B
�l���\�s�̐ԓS���������Ă����Ƃ��́A�{���ɂ��ꂵ�������B
�ʐ^���Ԃ��A�}���h�̂��������P�[�L���đ҂��Ă��Ă���āA�ԓS���̉��Łu�������߂łƂ�!�v�Əj���Ă���ĐH�ׂ��B
����5��20�������B�W����20�����p�h�����������������ƂɂȂ�B
�x�e�炵���x�e�͂Ƃ炸�A���ٓ�����ւŃJ�k�[�̏�ŐH�ׂ��B
�i���X�ɃJ�i�f�B�A����߂��ɍs������A�}�X�^�[���u�ǂ����牺���Ă���?�v�ƕ������̂ŁA�u�]��肩��v�Ɠ�����Ɓu����ł��̎��ԂɋA���Ă�����?!�v�Ɩڂ��ۂ����Ă����B
�����^�������P���~���Ă��̓X�̃`���V��������Č�����A�u3���Ԃ�6�L���v�Ə����Ă������̂ɁA�������͎����T�L���ȏ�ł������̂������B
�}�X�^�[������������������Ă�����A�����Ɓu�]��肾����?!�@�����A�����B�����Ƌ߂����牺�����ق���������v�ƃA�h�o�C�X���Ă���Ă����ɈႢ�Ȃ��B
�g�C���̂��ߎ~�܂����̂́A�|���|����1��B���͐쌴�łȂǂł����A�����͈�x���g�C���ɍs�����ɂU���Q�O���ɋA��Đ^����ɑ������B
�Ȃ�����������������B�����ł�����Ȃɑ̗͂�����Ƃ͎v���ĂȂ������B
�߂����Ɏ���_�߂����Ƃ��Ȃ��|���|�����A�u���������̗͂�����A�㓙�㓙�v�Ɨ[�т̎��ڂ����ƌ������B
����A�����������Ȃ��ɂ͕����܂���B�����āA�������܂��]���̏o���n�_�܂ŁA����ǂ͎���瑖���ĎԂ����ɍs���ƌ�������!!�B
 �ʐ^�͂���ȊO�S���w�������ʂ��ĂȂ������B�܂�������O�����ǁB
�ʐ^�͂���ȊO�S���w�������ʂ��ĂȂ������B�܂�������O�����ǁB
9��22��(��)����@�{�����e�B�A�i�Ђ݂��j
�L���R�����NPO�̉�����Ďl���\�s�ցB���̂��ƃC�x���g�̑ł����킹�ɍs���āA�u���{���������v�Ɓu�`�����e�B�[��d���W�v�̊���b�������Ă��܂����B
NPO�̂ق��́A���m�s�̉�Ёu���z�v����䂸���Ă�������p�C�v�֎q�̎g�p�ɂ��Ăł����B
�{�����e�B�A�����͑吨�̐l�ɏ����Ă�����Ă��܂��B��Ƃ���s�v�ɂȂ�������֎q��b�J�[�Ȃǂ������Ă��炢�A�����Ő��k�������g���Ă���̂ł��B
���i�����łȂ��A���낢��ȃC�x���g�ʼn�����Ă������郈���f��������A���肪������Ƃ̋��͂̃J�^�`���Ǝv���܂��B
���N���`�����e�B�[�̎�d���W���A��N�Ɠ��������f���M�������[�ōs���܂��B
�{�����e�B�A�̍�i�����łȂ��A�e��k�����̍�i��������āA���N���܂����낢��Ȍ𗬂̏�Ƃ��Ă��y����ł���������Ǝv���܂��B
�����̓J�k�[�Ŏl���\�쉺��ł��B���ݕ��A���َq�A���ւ��A�n�}�A�J�����E�E�E������ٓ����Y�ꂸ�ɁB
�����Ȃ��悤�ɁA�����ɐԓS���܂ʼn���邩��?
 �@�Q�l���J�i�f�B�A���ʼn���܂�
�@�Q�l���J�i�f�B�A���ʼn���܂�
9��20��(��)����@������i�Ђ݂��j
���N�͂��Ƃ̂ق��c�����������ł��ˁB����30�x���Ă��܂��B
����펪�������H�̖�����A�������肵�Ă��܂�! ����Ȃɑ����Ƃ͂т�����!
�u�́[�ƁE�炢�ӑ��v�ł́A��������Ƒ����Č���̈��ł����B�q�m�q�J���ł��B
�L���R���畷���Ă͂��܂������A�ق�ƂɃg���{����������!
���S�C�͂���Ǝv���܂��B���炵���X�s�[�h�Ŕ��ł���̂ɁA�Ђ傢�Ɛg�����킵�Č����ĂԂ���Ȃ��B�l�Ԃ��������Ԃ����Ă���Ƃ������炢�A��щ���Ă��܂��B
�o�b�^���J�G�����҂��҂���ɂ��܂��B�삤���������҂��Ă��܂������A���N�͏����Ȕ����F�̂˂��݂��o�Ă��܂����B
�p�b�ƌ��������ŁA�|���|���������Ȃ�Ƃ��˂��݂Ǝ�ނ������Ă���܂����B���������m�����A�|���|�������͖{���ɂ������̂ł��B
������āA�w�Z�ŏK���m���ł͂Ȃ��ł����?
���N���߂Ă������@��܂������A�傫�����̂�25�Z���`���炢�ɐ������Ă��܂��B
�܂��͈��͓�łӂ����Ă��������܂����B�y���g���L�̍g�F�̔���ƁA�z�R�z�R�̊Â������ł����B
��V�ɂ�����A�X�B�[�g�|�e�g��p�C�ɏĂ�����E�E�E�������������Ȃ�����A�Ă����ɂ��ĐH�ׂ����ȁB���������P���s��!
 �@�G�m�R���O�T�ɏH�̌�
�@�G�m�R���O�T�ɏH�̌�
9��18��(��)����@�S�͂��o����i�Ђ݂��j
�X�|�[�c���ϐ킵�Ċ�������̂́A�����ɏ��������܂�������������ł��傤�ˁB
�܂��Ă�q�ǂ������́A�����̑S�͂��o�����Đ킢�A�܂���B�܂��ɑS�g�S����ӂ肵�ڂ��Ă���̂ŁA���Ă��Ė{���Ɋ������܂��B
�����͉^����ł����B�V�C�ɂ��b�܂�A���낢��ȋ��Z���ƂĂ��݂������̂�����̂���ŁA��������ł����B
���ɂ́u�A���R�[���v�̐��������������̂������āA���q�̉�����2����܂����B�^����ł���Ȃ��Ƃ͏��߂Ăł��B
�Ō�͑����̐��k�����g�n�w�̏�ԂŁA���͂�s�����Ă��܂����B���ꂾ�����������A�̂̂����������ɂ��Ȃ��Ă����R�����m��܂���B
100�L���}���\���ɂ��ʂ��邱�Ƃł����A�����̗͂̌���������Ă݂�A�X�|�[�c�ł͂ƂĂ����m�Ɍ��ʂ��o�܂��B
�����Ă������Ă��A�S�͂�s���������Ƃɂ�閞�����ŁA����͂����Ən�����Ǝv���܂��ˁB
�X�|�[�c�����ł͖����̂�������܂���B���t���n�������ł��E�E�E�A����ȏ�w�͂̂��悤���Ȃ��Ƃ����A���肬��܂Ŋ撣���Ă݂邱�Ƃ�����Ȃ��Ǝv���܂��B
�u�������v�����Ƃ����̂́A����ȂƂ���ɂ���̂����m��܂���B
 �@���q�����̂͂��҂́A�D�̑務���łʂ������̂Ȃ̂��A�����ɂ��`���ł��ˁB
�@���q�����̂͂��҂́A�D�̑務���łʂ������̂Ȃ̂��A�����ɂ��`���ł��ˁB
9��17��(�y)����@��̎펪���i�Ђ݂��j
����������������u�H�v�B�}���W���V���Q�����[�ɍ炫����Ă��܂��B
�������������������ފ݂Ȃ̂ł��ˁB
�u�́[�ƁE�炢�ӑ��v�͏H������̃V�[�Y���ŁA�|���|������������g���N�^�[�ł������A�������������܂����B
��������́A�T�j�[���^�X�A�`���Q���T�C�A�t�e�A�卪�A�l�Q�A�͂������A��Ȃ��X�i�b�v�A�ꐡ���瓤�B
���ꂩ�狅���ނ�n�[�u�̎�A�ʎ�����������A����\��ŁA�Z���������ꂵ���G�߂ł��B
�L���R����͍����A���k�Ɂu�G�M�������Ă�?�v�Ǝ��₳�ꂽ�Ƃ��B
�u���A�l�M���Ǝv������������B��������G�M���m���̂����āA�y�̂̂܂Ȃ����������B�v
�C�J�ނ�̓�����������ŁA�L���R�������m��Ȃ��̂ł�����āA���k���u�l�̂��������v�ƌ������Ƃ��B
�l�M�ƊԈႦ���̂́A�����ɂ��L���R����炵���b�B
���܂��Ɂu�C�J�̖n�ƃ^�R�̖n�̈Ⴂ��������?�v�ƕ�����āA���������Ղ�Ղ����Ƃ��B�܂��܂��������ꂽ���Ƃ́A�����܂ł�����܂���B
9��14��(��)����@�ӂ邳�Ə���i�Ђ݂��j
���Ă𑗂����A�h���[����A����̃��[�����͂��܂����B
�u�ӂ邳�Ə���݂����v�Ƃ��ꂵ�����t�������Ă��������Ă��āA���[����Ȃ̂����z���Ȃ��ƁA�����ĉ��߂ċC�Â��܂����B
�c��ڂł��Ă���Ă�l�A���̂��Ă�H�ׂĂ�������l�A���݂�����̌�����W�ŁA�ǂ�Ȍi�F�̒��łǂ�Ȃӂ��Ɉ�������E�E�E�܂肨�Ă̂ӂ邳�Ƃ����т̌������ɕ����Ԃ̂ł��B
�u���Ă̒����̂��q����́A�܂���������Ƃ������l�������v�ƃ|���|���������b���Ă���܂����B
�u����ł����x�����̏Z���Ɩ��O�������Ă���ƁA�Ȃ��e�ʂ̐l�̂悤�ȋC�����Ă���̂�ˁv�ƃL���R����B
�ŋ߂͒����̃��[���Ɂu�����o�Y�\��ł��B3�l�ڂł��v�Ƃ��ߋ��������Ă����l�����āA��w����ȋC�����������Ȃ��Ă���悤�ł��B
�u�́[�ƁE�炢�ӑ��v�̒I�c�Ŗ��_��ł��Ă���Ă�悤�ɂȂ��āA����10���N�B
������A�ŏ��̂��q����Ƃ̂������́A���̂܂ɂ�����قnjÂ��Ȃ��Ă���킯�ł��B
�ɖ쒬�́u�V�����v����Ƃ����A���_��̐H�i���z���Ă��邨�X�ł����B
�������Ŕ����ċA���āA���Ăɂ��Ĕ̔����Ă��܂����B�q�ǂ�����̚b���������H�ו��̂��Ƃ��l����悤�ɂȂ����̂������ł��B
���m�s��썑�s����u�f�l���k����v(���낽����ƌĂ�ł��܂���)�̃����o�[���A�����u�́[�ƁE�炢�ӑ��v�ɂ���ė��Ă����̂��A10�N�ȏ���̘̂b�ɂȂ�܂����B
�ŋ߁A�|���|�������ƃL���R����͓������Ȃ��������āA�悭�b�����Ă��܂��B
10�N�����āA������x�����o�[�Ɖ����ł��Ȃ����Ȃ��A��d���W�Ƃ���肽���˂��A�Ɠ�l�͖����Ă��܂��B
 �@�����̈������������ł��B�䕗���܂���悤�ɁE�E�E�B
�@�����̈������������ł��B�䕗���܂���悤�ɁE�E�E�B
�X��11��(��)�J�̂��܂�@�^�[�V���E�e���[�_�[�i�Ђ݂��j
����Ă���Ίy�����v�悪�������̂ł����A�J�ł�����B
�݂�Ȃ������肷�钆�ŁA1�l���ꂵ�����������̂��L���R����ł����B
�u�^�[�V���E�e���[�_�[�̊ӏ܉�ɐ�ւ��܂��傤!�v
�^�[�V���̓L���R����20�N���������ꑱ���Ă��鏗���ł��B
�A�����J�̃o�[�����g�B�ɏZ��ł��āA���R�Ƌ������Ȃ���G��`���Ă��邨������B
�L���R����Ƀ^�[�V�����Љ���̂́A���m�����\����f�U�C�i�[�̓T�q����ł����B
�����u�قɂ�v�̐�ƕ���ŁA���c���܂݂����ȑ��݂́u�A�n�i�x�b�N�v�̃I�[�i�[�ł��B
�^�[�V���M���`�������L���R������A���ꂩ�炱�Ƃ��邲�Ƃɂ݂�ȂɏЉ�Ă��܂��B
NHK��2���Ԃ̓��W��g�̂��A�S���Ƀ^�[�V���t�@���������Ă��邩��ł��傤�ˁB
�u�K���Ƃ́A�S���[������邱�Ɓv
�u�����������Ƃ͎v���܂���B�܂�A�l���ɉ������Ȃ��Ƃ������Ƃł��傤�ˁv
�u���l�̂���ǂ����Ƃ́A���Ԃ���Ԃ���������́v
�u�l�͎�����������Ă��闧��������̂����ɂ��邯��ǁA���̐��Ő�������̂́A�����オ���Ď����̖]�ޏ�T���ɍs���l�A������Ȃ�������n��o���l�ł��v
�Ō�́u�@�v�̓^�[�V���̍��E�̖��������B������{��ԑg�̃^�C�g�����u�y���݂͑n��o������̂�v�Ȃ̂ł��ˁB
90�̍����^�[�V���́A���Ɍ������Đ��������ƕ�炵�Ă��܂����B�|���|���̕��𒅂Ă���̂ɁA�������X�e�L�ŋP���Č����܂����B
�����Z���ꐶ����Ȃ�A���{�b�g�⎕�Ԃ̂悤�ɓ��������̂ł͂Ȃ��A�ꍏ�ꍏ��S�����߂ĕ�炵�����Ǝv�킸�ɂ͂����܂���B
9��9��(��)�����@NHK����W�i�Ђ݂��j
�����ANHK����|���|�������̎�ނ�����܂����B
���N�̃J�����_�[�̓��܍�i�́A����W����S���ŊJ�Â����̂ł��B
�W���̂Ƃ��Z���R�����g���Y������Ƃ������ƂŁA���낢�땷����܂����B
��ނ��钆�œ�����������܂��B
�܂��A�c��ڂ̎ʐ^�͉��吔���ƂĂ����������Ƃ������ƁB���{�͐���̍�������A�c��ڂ͌����i�Ȃ̂ł��傤�ˁB
�����āA�N��Ƃ��Ă͎Ⴂ�ق����Ƃ������ƁB�x�e���������������B
����̒��ō�����܂����Ƃ́A�{���ɍK�^(?!)�ł����B
�u���d����?�v
�u�Ƌ������Ă��܂��v
�u����A���Ⴀ�ʐ^�Ƃ͒��ڊW�Ȃ��̂ł��ˁB�ʐ^���n�߂邫�������͉��������̂ł���?�v
�u�͂��B�Ƌ�̎ʐ^���B�낤�Ǝv���āA�J���`���[�����ɍs������ł��v
�u������������ł����B�o���N���͉��N���炢�ł���?�v
�u5�N�ł��v
�u��܍�i���B��ꂽ�Ƃ��̂��Ƃ��A���������肦�܂���?�@��͂�B�����Ƃ��ɋ����育�����̂悤�Ȃ��̂��A�������ɂȂ����̂ł��傤��?�v
�u����A����́E�E�E�悳�����Ղ�̎B�e�ɍs�����A�肾������ł���B���܂��ܗz�����������c��ڂ��ƂĂ����ꂢ��������ŁE�E�E�v
�|���|�������炵���A�p�c�ɐ����ɓ����Ă��܂����B
�S������̓���������������A�܂����m�点���܂��B
 �@�|���|���H�[�̃e�[�u���B9��6�������̎G���u�a������炵�����v�ɏo�Ă܂��B
�@�|���|���H�[�̃e�[�u���B9��6�������̎G���u�a������炵�����v�ɏo�Ă܂��B
9���U��(��)�䕗14���\���J�@
���N���N�A���m���͑䕗�ɂ͊���Ă���Ƃ͂����A����͂��Ȃ�̌������ƒ����Ԃ������B
�����͈�����A���̉����Ȃ���Ƃ̒��ʼn߂������B
����d���̋A��ɃX�[�p�[�Ɋ������A�H�������ސl�ł��ӂ�Ă����B
�u�����͐Q�邵���Ȃ���v�Ƃ�����b�����ɂ����B
�Q��Ȃ�ĂƂ�ł��Ȃ��B���̓����Ƃ̒��ł�邱�Ƃ͂����ς��B
���܂�Ă������e�����A���ތ����ȂǂȂǁB���̊Ԃɓd�b����B
�ŏ��͐}���ق̃~�L�����B�u�L���R����A�ׁ[�O���Ă��Ă���Ƃ���Ȃ��ǁA�Ñ�Ă��ς��炢���F�Ȃ́B�m���Ñ�Ăł����߂����ł������?�v�Ƃ����₢���킹�B
�����A�������_�̒��Ԃ�B(��)
���ߕ��̓A�h�o�C�X�ł��邪�A�Ñ�Ăׁ̂[�O���Ȃ�ďĂ������Ƃ��Ȃ��B�����������A������!
�ƃ~�L�����Ƀ��V�s���˂������B
���̓��`���[�h�v�l����B���ނ��т̐����o���ŖZ���������������A�b���o���ƂƂ܂�Ȃ��Ȃ��āA�����ꎞ�Ԉȏ�b���Ă��܂��B
�u��̃~���U�ƃp�p�C������Ȃ��́v�ƁA���`���[�h�@�̎������p�B
�������A�[�`���|��A��̑��Ԃ��Ȃ��|����āA�~���U�����������Ă���E�E�E�Ƙb�����B
�~���U�͏㕔���ɂ��ĕ��J���܂Ƃ��Ɏ₷���̂��A����|��Ă��܂��B
�Ђ��Ђ�낵�Ă��郆�[�J���̂ق����A���̂悤�ɂ��Ȃ₩�ɓ|��Ȃ��B
�������ł܂��܂��B����͉Ƃ��~�V�~�V�h��Ă���B���A�ߌ�4�������ǁA��ԂЂǂ��������B
���R�̖҈Ђ̑O�ɂ͂Ȃ����ׂ��Ȃ����ǁA�ǂ�����Q������ȏ㑽���o�܂���悤�ɁE�E�E�B
 �@���̉Ă��璇�ԓ��肵���K�K�u�^�B���O�Ɏ�����Ȃ��Ԃł���?
�@���̉Ă��璇�ԓ��肵���K�K�u�^�B���O�Ɏ�����Ȃ��Ԃł���?
9��4��(��)�J�@��d���W�̌v��i�Ђ݂��j
�|���|�������́A������ǂ�T�b�J�[�̎B�e�ցB
�L���R����͗��܂�Ă������ߋ����ցB�䕗�̉e���ʼnJ���������A�S�z���Ȃ���o�����܂����B
�ł��A�M�S�ȎQ���҂݂̂Ȃ���Ɗy�������Ԃ��߂����āA�ق��Ƃ��ċA���Ă��܂����B
�����ɂ͕a�C�Ɠ����Ă���l�����āA�u��������A���Ă�?�v�ƃ|���|���������C�ɂ����Ă��܂����B
�u����A���Ă��B���C�����ɂȂ��Ă��āA�悩�����B�v
�����̎Q���҂݂̂Ȃ���́A�悭����K�˂����ƌ����܂��B�t�G������A���������͋����̂��Ƃ��Ă������Ƃ���ł����B
�ˑR�̂��q���܂����܂��B����́u�V���Ō��āA�S�Ɏc���Ă����̂ł��v�ƁA��������T���ė���ꂽ��v�w�ł����B
�u���̎�d���W�̂Ƃ��́A���m�点���������v�ƁA���h��n���ċA���܂����B
�u���������A���낻���d���W�̋G�߂˂��v�̂�т肵����l�́A����ƋC�Â����݂����Ɍv��𗧂Ďn�߂܂����B
���N�͐V���������o�[��������āA�W���Ƌ����̗�������肽���Ƙb���Ă��܂��B���肵�����A���m�点���܂��ˁB
 �@��̓q���g���m�I�̋G�߂ł��B
�@��̓q���g���m�I�̋G�߂ł��B
�X��2��(��)�����@�u�́[�ƁE�炢�ӑ��v�̒��Ɩ�i�Ђ݂��j
���͂T��30�����A�Y�{�V���[�́u�R�P�R�b�R�[�v�̉̐�����n�܂�܂��B
�V���[�͂S���ɑ��ɗ��āA�Q�������炢����̂��n�߂܂����B
�ŏ��͉̂�����̂�Ȃ�������ł������A�܂��Ȃ��������������̂��悤�ɂȂ�܂����B
���̎��Ԃɂ͉Ƃ̒��́A�����������������ς��ɕY���Ă��܂��B
���т�������p���������肢�낢��ł����A�Ƃɂ��������Ŏn�܂邱�Ƃɂ͕ς�肠��܂���B
�L���R����́A���V���[�̉̂Ŗڊo�߂āA�����������̒����g���g���ƊK�i������čs�������A��ԍK����������ƌ����܂��B
�p����������o���āA��܂��Ă���ԂɃR�[�q�[�����A���ւɐV�������ɍs���܂��B
����̎n�܂�̂��̊Ԃ̐Î�B�₪�āA���z���������ݎn�߂�Ɗ����J�n�ł��B
�u�����̎��ԁv��A������́A�閰�鎞�B
������I����āA���Ђ��܂̓����̃V�[�c�̏�ł���������葫�����[��ƐL���B
���̉������₩�ɋ����n��A�����猎��������ō�!�@�x�b�h���璭�߂�R�́A���X�Ƃ����V���G�b�g�Ŗ��ɕ�����ł��܂��B
�Â��ȐÂ��ȁu�́[�ƁE�炢�ӑ��v�̖邪�X���Ă����܂��B
 �@����1.5�҂̃p�����Ă��܂��B�����̓V�i�����p���B
�@����1.5�҂̃p�����Ă��܂��B�����̓V�i�����p���B
2005�N8���̕�炵
8��27��(�y)�����@�@�Ő��߂�i�Ђ݂��j
�����݂͂�Ȃł��邨���ɍs���Ă��܂����B
�Ԃ�1����30���قǂ̂Ƃ���ɂ��邨���ł����A�L���R���Z�E����u�@�Ŏ�����߂Ăق����v�Ƃ����˗���������ł��B
�u�@?�@��x�����߂����ƂȂ����ǁA�������낻��!�v
�Ȃ�ł�����Ă݂�����L���R����́A��OK�ł����B
�����̓�����t�߂ɂ���c��ڂɁA�Ñ�@����������炢�Ă��܂����B
��ɂȂ����̂́A����͂���Ō`���������낭�āA�u�́[�ƁE�炢�ӑ��v�ł��Ñ�@����Ă邱�Ƃɂ��܂����B
�K���߂��ɗV��ł���c��ڂ�����܂��B�|���|���������u�������A���̓c��ڂ������ˁv�Ƃ���������C�ł��B
�A���ƃL���R����͂��������A�@���ςĐ��߉t���̂�A�V���N�X�g�[���Ɩȃ��[���̃n���J�`����߂Ă��܂��B
�V���N�͂ƂĂ��a���Ђ�F�ɐ��܂�A�ȃ��[���͒W�����F�ɐ��܂�܂����B�}���̓~���E�o���ł��B
�@�͐��̂܂g���܂������A�h���C�ɂ���Ƃ܂�������F�ɂȂ�ł��傤���A����S�Ŕ}������Ƃǂ�ȐF�ɂȂ�̂ł��傤�B
���߂����������́A���X�ݏZ��T�����f�U�C�����ĐD��\�肾�����ł��B
�ʐ^�ł��Ƃ�D��@�A��i���f�ڂ��ꂽ�G���Ȃǂ�q�����܂������A�ƂĂ��X�e�L�ȕ��ł����B
 �@�Ñ�@�͂ƂĂ������͂��������B
�@�Ñ�@�͂ƂĂ������͂��������B
8��25��(��)����@�l���A�C�����h���[�O�ƃ����L�[�搶�i�Ђ݂��j
�ߌォ��݂�Ȃŏh�юs�ɏo�����܂����B
26�N�Ԃ�ɏh�юs�Ńv���싅�̎������s���A���̊ϐ�ƃ����L�[�搶�̍u����ł��B
���m�t�@�C�e�B���O�h�b�O�X�́A�s�b�`���[���n���o�g�Ƃ����ĉ������ɂ��₩�B
2-0�Ŋ��������ł����B
�I����A������Ɛ��ċq���������Ă��ꂽ�̂ɂ͂т�����B�T�C����ʐ^�ɂ����܂�ȂǁA�t�@���T�[�r�X�������ł����B
6�����烄���L�[�搶���Ƌ`�Ɛ搶�̋���u����ցB���ɒ����ƒ����ł��Ă��āA�l�C�̂قǂ����������܂����B
���������͖{�œǂ�ł����̂ł��������m���Ă��܂������A���{�l�̌����畷���Ƃ܂������ɂނ��̂�����܂��ˁB
���e�̗����ŕ�e��m�炸�Ɉ炿�A�ƒ�ɂ��w�Z�ɂ����ꏊ���Ȃ��A�����߂����q�B�N�������Ă���Ȃ��̂ŁA��������邽�߂ɖ\�͂��ӂ邢�s�ǂƌĂ�E�E�E���Z���ނցB
1�N�Ԃ̂Ђ�������̂̂��A�k�C���̖k���]�s���Z�ցB�����ň��B�搶�Əo��A�ނ͏��߂ĐM�������l�����邱�Ƃ�m��̂ł��B
����݂���̖{�u�D�����ɏo����āv�������ł����A�܂���1�l�̋��t�Ƃ̏o����A���̐l�̐l����ς��Ă������̂ł��B
�搶�����瓖�R�ƌ����܂����A�b�p���������肵�Ă���̂ŕ����₷���A���J�Ȍ����ł����B
���������k���������A�܂��Ă����̂��A���ꂵ�������ł��B
�`�Ɛ搶�͍��A���t����߂ċ���ψ��̎d�������Ă��܂����A�S���̔Y�߂��҂����ɉe����^���Ă��邱�Ƃ́A����ς�u�搶�v�Ȃ̂��Ǝv���܂��B
12���ɂ́u����搶�v�̍u����ɂ��A�݂�Ȃŏo������\��ł��B
 ���Č������B�C���^�r���[�ɓ�����s�b�`���[�B
���Č������B�C���^�r���[�ɓ�����s�b�`���[�B
8��21��(��)�܂�Ƃ��ǂ��J�@����������i�Ђ݂��j
�y�������s�̂���������ŁA�C�x���g������o�����܂����B
���N��2�N�ڂł����A�n���݂̂Ȃ��ƂĂ������������ŁA�|���|���������L���R�������������y����ł��镗�ł����B
�u�؍H�R�[�i�[�v�u�L�k�H�R�[�i�[�v�u�w���v�R�[�i�[�v�u�̍����R�[�i�[�v�u��������߃R�[�i�[�v�Ȃǂ�����A�Q������ƒ��H�����Ă��܂��B
���ɂ���A�Ă��Ƃ�A�Ƃ���Ă�A�����X�ȂǁA��������OK�ł����B
���N�|���|�������̖؍H�����́A�q�ǂ������ɑ�l�C�B�L�B�[�z���_�[�A�X�̎��v�A�x���`�����j���[�ł������A���H���Ƃ鎞�Ԃ��Ȃ��u�����v�u�����v�R�[���������Ă��܂����ˁB
�����ō�����y���_���g����ɂ����āA�u�ڂ��A�����D��!�v�ƌ����Ă�����w�N���炢�̏��N�����܂����B
�ڂ��P�����āA�ق�Ƃ��Ɍւ炵�����ł����B����̊�т́A��͂肱�����������ł͔����Ȃ��Ƃ���ɂ���܂��ˁB
�݂�Ȃ��������ɔ��Ă܂������A�����C�x���g�ɎQ���ł������ꂵ���͊i�ʂł����B

8��18��(��)����@��W���[�X�i�Ђ݂��j
�������{�����e�B�A����������܂����B
�l���\�s�̗c�t���̐搶���������ɂȂ��āA���낢�남�b���܂����B
�u�̂͂����ƈ��������ۂ��������������q�������������ǁA���͎��͂Ɏ��������킹�悤�Ƃ���q�������v
�u���R�̌��A�����̌������Ȃ��Ȃ��Ă���悤�Ɋ�����v
�u�q�ǂ��̖{���͕ς���Ă��Ȃ��̂����ǁA��l��Љ�ς�������ƂŁA�q�ǂ����e�����Ă���̂��Ǝv���v
�L���R����͂�����ɂ���Ƃ��Ȃ����ĕ����Ă��܂����B
�����āA�u���́A���w�Z�̐搶������A���Z�̐搶������A�������蓯�����Ƃ�����������̂ł��B������w�Z�ł���������_�����X����܂��v�Ɣ������Ă��܂����B
�c�t���̐搶�����́A������Ė����Ă���A���R�̂��̂𗘗p���ėV����������A���낢��w�͂���Ă��邻���ł��B
���������|���|�������̍�i�́A�c���Ɉ��|�I�Ȑl�C������܂��ˁB�v���o���܂����B
�K���߂Â��ė��āA�ڂ��P�����Ď��L���̂ł��B�ǂ̎q���K���A�{���ɕs�v�c�ł��B
�悿�悿�����̐Ԃ������A���������̐����Ȋ����݂̂Ŗ�����ċ߂Â��̂��Ǝv���̂ł��B
�v���X�`�b�N�̐��I�Ȃ�������ł͂Ȃ��A�f�p�Ȗ̎}�̈֎q���A�q�ǂ��̐S�ɖL���ȑz���͂��������ĂĂ��邱�Ƃ͊ԈႢ����܂���B
�c�����Ɂu�ق���̂̊��������ɑ���v�A�݂�ȂŊm�F������������ł����B
�x�e���ԂɃL���R���A�匎�����Y�́u��W���[�X�v���o���Ă���܂����B
���������Ă��������ɂȂ����炠��܂肨�����������̂ŁA���Ђ������E�E�E�Ƃ̂��Ƃł����B
�~�V���E���Ƃ����݂���̃W���[�X�������ł����A�{���ɂ���₩�ň��ݐS�n���悭�ď��߂Ă̖��ł����B
9���܂ł̋G�ߌ��肾�����ł����A����͂��Д���Ȃ�����Ƃ�������t�@���ɂȂ�܂����B
 �@�����~�V���E���ł��B�u���^���Ɏ��Ă��܂����A�T�C�Y�������������͑S�R�ʁB
�@�����~�V���E���ł��B�u���^���Ɏ��Ă��܂����A�T�C�Y�������������͑S�R�ʁB
8���P�T��(��)����@�L�X�ނ���D���E�務�܁i�Ђ݂��j
���N�W���P�T���ɂ͓���̕l�ӂŁu�L�X�ނ���v������A�|���|���������o�ꂵ�Ă��܂��B
����܂ł͂Q�ʂ��ō��ŁA�S�ʂ�������V�ʂ��������Ƃ��E�E�E�B
�|���|�������̐��i���炵�āA���N�����P�ʂ��˂���Ă����̂ł��傤�ˁB
�݂��ƗD���A���킹�đ務�܂��l�����������ŁA�^�����Ȋ�łɂ��ɂ����Ȃ���A���Ă��܂����B
�D���̏ܕi�͑傫�ȃN�[���[�ŁA�務�܂̂ق��̓��b�h�P�[�X�ł����B
���������[�H�̂������ɃL�X�����������܂������A�D�������L�X��24.5�Z���`�B�Q�ʂƂ̍���0.5�Z���`�����������ł��B
�務�܂̂ق��͕C���ŏ����Ƃ��ŁA�L�X�̂ق��ɃR�`�Q�C���܂����Ă��܂������A�܂������Ă��܂����B
�u�R�`�͂Ԃ�ɂ��Ė��X�`�ɂ���Ƃ��܂���v�Ƃ����ꐺ�ŁA�L���R���������X�`�ɂ��܂����B
�L�X�͔��g�̏�i�Ȗ��ŁA�R�`�̓j���Ƃ��������悭�Ă������������ł���B
�P�T���͂���܂����N�́u�ԉΑ��v�B���N�̓��C����A�\�����ƁA���˂܂��Ƃ����獇�킹�����������ŁA�u�݂Ȃ���䂩���p�����܂��Ă����v�ƃL���R�����Ă���܂����B
�u���N�͎����s�������Ȃ��v�ƌ����ƁA�u�Ђ݂�����A�́[�ƁE�炢�ӑ��̂͂��҂�����āA�݂�Ȃŗx��Ȃ�?�v���āB�L���R����͂܂���ł�����B������̏ܕi�̓r�[�����������ł��B
 �@�D�������߂��P�C�A������܂����?
�@�D�������߂��P�C�A������܂����?
8��14��(��)�����@���~�i�Ђ݂��j
�Q���A���̃{�����e�B�A�������I���A�������炨�~�x�݂ł��B
�ƌ����Ă��A���~�͐e�ʎ���◈�q�������āA��w�͋x�݂ǂ��낶�Ⴀ��܂��ǂˁB
���ɏ����́u���~�v�̉Ƃɔq�݂ɍs���̂ŁA���������~�������肷��Ƒ�ςł��B
�}����ق��͂����Ƒ�ςł��傤�B�T���`������h�g�A�^�^�L�A�\�[�����A�t���[�c�E�E�E�Ƃ����̂���Ԃł��傤���B
�u�́[�ƁE�炢�ӑ��v�͂ӂ��̂��~�Ȃ̂ŁA�ϕ��Ƃ����i�A�ʕ��A�[���[�A�炭����Ȃǂ��Ղ�܂����B
�����i�̓L���R���悭����Ă����̂́A���̊������i�A�T���_�C�ۊ������i�A���Ȃ���i�Ȃǂł��B
����̃u�V���J���̐|������œ����̂ŁA���肪�ƂĂ��悭�Ă��������ł���B���̋G�߂͂��Ȃ���i�̋�ɁA���̂������œ���Ă����������ł��ˁB���Ђ���������B
�����P�T���̓|���|�������̓L�X�ނ���B��͊C�ӂ̉ԉΑ��ł��B
 �@�Ă̓C�x���g�������ς�(�|���|�������B�e)
�@�Ă̓C�x���g�������ς�(�|���|�������B�e)
8��12��(��)���� �@�{�����e�B�A�i�Ђ݂��j
�����A�u�́[�ƁE�炢�ӑ��v�ł́A�{�����e�B�A����������܂����B
���s������L���R���A�u�Ђ݂�������ĉ���? ���Ė₢���킹�������ρ[�[�����������B���ӂ��v�Ƃ��ꂵ�����ɏ��܂����B
���́u�������낪�艮�v�Ƃ����L���R���������āA��������y����ł��܂��B
�������q������A�L���R������Ă���u�q�ǂ��̎����x�������v�̃{�����e�B�A�̂P�l�ł��B
�f���̂���݂�������̂P�l�ł����A�u��̎�d�����Ԃ����v�̍�Ƃ������قƂ�ǂ��{�����e�B�A�Ƃ��ĉ�����Ă��܂��B
���낢��Ȑl���u�t�ɂȂ��āA�������݂�ȂŊy���݁A�𗬂ɂ���Ďx�����������Ƃ����̂��A�L���R����̊肢�ł��B
���̓{�����e�B�A�͏��߂ĂŁA�ŏ��͎q�ǂ������̖��ɗ��Ă�����ȂƂ����C�����ł����B
�ł��A�r���ŋC�����܂����B�{�����e�B�A���Ď����̂��߂Ȃ�ł��ˁB�������������̂��͂邩�ɑ傫���������A���낢��Ȑl�X�Ƃ̏o������̍��Y�ɂȂ��Ă��܂��B
���ꂩ��̃C�x���g�́A21��(��)�ɓy�������s�̂���������ŁA�؍H����߂̋���������܂��B�݂�ȂŎQ������\��ł��B
�����Ԃ��ʂ��āu�K���[�W�M�������[�v�̏������A�������i�߂Ă��܂��B
 �@�����͖ڂ��o�߂�悤�ɂ��ꂢ�ȃV���N�̃^���N�g�b�v�B�吳����̒����̃����C�N�ł��B
�@�����͖ڂ��o�߂�悤�ɂ��ꂢ�ȃV���N�̃^���N�g�b�v�B�吳����̒����̃����C�N�ł��B
8��11��(��)����@�����A�i�Ђ݂��j
�݂Ȃ��܁A����ɂ���!
��������Ǘ��l���o�g���^�b�`�����A���l�Q���̂Ђ݂��ł��B(���Ȃ݂ɂP���͑��q����)�B
�|���|�������A�L���R����ɑ����āA���������z�[���y�[�W��`�����e�B�̊���S�����܂��̂ŁA�ǂ�����낵�����肢���܂��B
�������ƂĂ��������ł������A�|���|�������͂��������ƒP�ԂŁu�悳�����Ղ�v�̎B�e�ցB
�L���R����́u�}�H�N���u�v�̌��C��ɏo�����܂����B
�[���A�u���C����̂������ŁA�v���Ԃ�ɗ����߂̎t���ɂ�������A���`���[�h�v�l��������ɂ���āA�悩�����[�[�B�l�Ƃ̏o����āA���肪������˂��v�Ƒ��тŋA���Ă��܂����B
�����ł͈�Ԗ{�i�I�ɗ����߂�����Ă���Ƃ���M�搶�̍�i�������Ă��炢�܂������A�L���R����^����Ƃ���A���̐F���[���ĂƂĂ����ꂢ�ł����B
M�搶�͗��t��100���Ԃ������Ĕ��y�������������ɁA�킴�킴�y�������s�̏㎿�̖̊D��n�����A���{����ΊD�łӂ����є��y���������t������Ă��������邻���ł��B
�������ăT�b�Ɨn�����������Ƃ́A�S�R����ē��R�ł���ˁB
�u�Ђ݂�����A�����Ē�������E�ی��ʂ������ł����āB������̂���_��ƂȂǂŁA�ŎւȂǂ���g������ڂ����Ă���������B�̂ɂ��n���ɂ��D�������F��ˁ[�v
�L���R����̉��(?)�͂����ƒ����������̂ł����A�ڂ����̓����N��M�搶�̃z�[���y�[�W������������ˁB
�ʐ^�͏��2����M�搶�̐V��B��ԉ��̃`�F�b�N���AM�搶�ɋ����Ă����������L���R����̍�i�ł��B
�{�l���킭�A�u������ׂ�ɖ����ɂȂ��āA���ߎ��Ԃ�Y��Ă��܂��Ď��s�����v�Ƃ̂��ƁB
�e�B�[�}�b�g�̕z��M�搶�̐D��ŁA�搶�̃z�[���y�[�W�ō�i�̍w�����\�ł��B

8��9��(��)����@�Ǘ��l�̌��
�݂Ȃ���A�����ԃL���R�́u���ւ�v��ǂ�ł��������A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B
�p�\�R���I���`�̎��B���͂��Ђǂ��ēǂݕԂ��Ƌ�ł����A����Ȃɒ��������Ƃ͎v���Ă����Ȃ������B�݂Ȃ���̂������ł��B
�����ԑO����A�F�B�̂Ђ݂�����Ƒ��q����Ɂu�Ǘ��l����Ă݂�?�v�Ƃ��������Ă����̂ł����A����Ђ݂�����ɑ_�����߂ăE�������킹�������t���܂����B
�������A���q�������`���Ă����Ǝv���܂����A�L���R���ł��邾���f���ɏ������݂����Ǝv���Ă��܂��B
�Ђ݂�����͎��ȏ�Ƀp�\�R�����ӎ��������̂ł����A���������Ǝv���܂��̂ŁA�݂Ȃ��ꂩ��ǂ�����낵�����肢�������܂��B
8��2��(��)����@�ς��Ȃ����i
�����R�V�q�J���̈��������B
���V���ɍs���鑁���Ă̈��́A���N�������C�s�̂悤�Ȉ�����B
�̒����犾���ӂ��o���A���炽��Ɨ����̂�������B�ڂɓ���Ɵ��݂Ēɂ��B������͔����S�t���o�Ă��āA���p�ɂ��т���B
����ł��̂ɔ�ׂ���A�����Ƃ����Ƃ��[�[�[�Ɗy�B����ɁA�����͔����������̂ŁA�������������B
�o�b�^���҂��т���ђ��ˁA�g���{���Ԃ��肻���ɂȂ��Ă��������ԕ��i�́A���N���ς��Ȃ��B���H�ɂ̓��_�J�������ς��j���ł���B
���N�ς��Ȃ����i�ɁA�Ȃ��ق��Ƃ���B���ꂪ�����A�u���N�̓g���{�����Ȃ��Ȃ��v�Ƃ��A�u�Ȃ����_�J�̎p�������Ȃ��ˁv�Ȃ�Ă��ƂɂȂ�����E�E�E�B
���N�O���玄�́A�u�c��ڂɕω��̂���������������ǂ����悤�v�ƐS�z���Ă���B���Ă����̂̓|���|���̗͂����ł͂Ȃ��A���R�̒��̂��낢��ȏ������������Ă���Ă��邱�Ƃ�m���Ă��邩�炾�B
������A�|���|���́A�����̒��Ԃ���邽�߂ɔ_��͂��������g��Ȃ��B
���������ς��ŁA��y�̂��S������ɏ��Ă��A��łɋȂ��Ȃ��B
�ł��A�n���S�̂��a��ł���B���g���̉e���͂����悤���Ȃ��A���낢��ȕω������̂т���Ă���C������̂��B
�u�ς��Ȃ����i�v�́A���܂ő������낤��?
 �@�g���{�͕�����Ǝv�����ǁA�o�b�^�͌����邩��?
�@�g���{�͕�����Ǝv�����ǁA�o�b�^�͌����邩��?